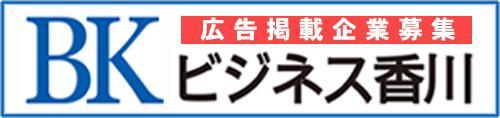水蒸気が立ち昇る番の洲の工場景(1972年 高1冬)
坂出市の沖合の浅瀬一帯を“番の州”といいます。アマモの茂る遠浅の海でした。浜街道と番の州町(埋立後の町名)に向かう県道が分岐する辺りには海水浴場があり、近くに住んでいた私は、夏休みには毎日のように海水浴に通っていました。子どもの目には波間に見える沙弥島(しゃみじま)と瀬居島(せいじま)は遠い場所に思えたものです。
番の州埋立事業は、香川県が工業県に発展するための一大事業でした。1964(昭和39)年、小学2年のとき埋立が始まりました。海水浴場の沖合に備讃航路の浚渫土砂が投入され、数年後にはなんと沙弥島、瀬居島が陸続きになったのです。見慣れた海と島の風景が、620万平方メートルの大地に変わり、瀬戸内有数の臨海工業団地となりました。
1974(昭和49)年、高校3年の冬にその事件は起こりました。12月8日の夜、岡山県倉敷市の水島コンビナートにある製油所から大量のC重油が流出し、北西風に煽られた重油は瞬く間に対岸の香川の島や港、海岸を黒く覆いました。汚染は紀伊水道に及び漁業は甚大な損害を被ったのです。
瀬戸内海もこれで終わりだと本気で思ったものです。その後も黒い油の塊であるタールボールが砂浜や海底に長い間みられました。
また、全国的な建設ブームで瀬戸内海は格好の海砂利の採取場になりました。1970年代中頃からは水質汚濁が原因で赤潮が頻繁に発生しました。「工場からの汚泥でシャコは全く獲れんようになった」。高校時代にお会いした豊浜の老漁師の怒りに満ちた姿が今でも印象に残っています。
これまで私たちは瀬戸内海から多くの恩恵を享受してきました。同時に人間の様々な営為はこの海を翻弄し続けてきたともいえます。「海の復権」を掲げる瀬戸内国際芸術祭がまもなく始まります。この多島海を次代にどう継承していくか。海と共生した生業や暮らしをどう創り持続させるか。瀬戸内海や島々の大切さに向き合うとても大切な時期を迎えています。
(文・絵 工代 祐司)
おすすめ記事
-
2026.01.01

四国の暮らしを支える道路網を
未来に継承したい西日本高速道路 執行役員・四国支社長 喜久里 真二さん
-
2026.01.01

“移動”を支えるプラットフォーマーへ
トヨタカローラ香川 社長 向井 良太郎さん
-
2025.12.18

四国の空を支える若き翼
ヘリ運航と整備の最前線から四国航空 運航課・山﨑和輝さん/整備課・足立忠則さん
-
2025.12.04

財産は「人」。安全・安心・快適を届ける
西日本高速道路エンジニアリング四国
社長 後藤 由成さん -
2025.10.16

安全な空の旅を、地上で支える運航支援
高松商運空港営業所 安藝亮介さん
-
2025.10.01

JALと四国機構
英旅行会社に四国PR四国ツーリズム創造機構
-
2025.08.21

空港のもう一つの出発口
物流を支える貨物カウンター四国航空サービス事業部 貨物グループ 瀧本良美さん/梶谷幸子さん
-
2025.06.17

四国最大級の洗車場
ヤマウチセルフ多肥にオープン株式会社 ヤマウチ
-
2025.06.19

20種以上の資格を武器に
空港の裏方で光る専門職高松商運空港営業所 牛尾 拓己さん
-
2025.04.03

香川の未来に思いを馳せる
日本銀行 高松支店 支店長 大塚 竜
-
2024.12.19

自社一貫施工で「街の光」をつなぐ
株式会社三友電工