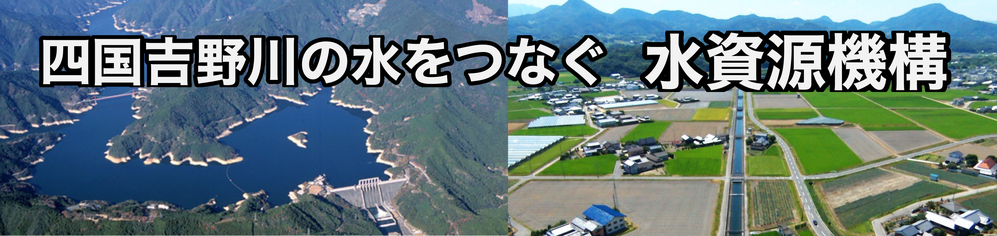多度津資料館にある陣屋模型(南西の方向から見る)
香川氏が去った後、生駒、山崎時代には多度津は荒廃したようですが、丸亀京極藩が成立してから36年後の元禄7年(1694)、二代目藩主高豊(たかとよ)の四男高通(たかみち)が1万石を分与されたことにより多度津藩が成立します。讃岐では三番目の藩でした。領域は、現在の多度津町全域と、善通寺市碑殿町及び三豊市の詫間町松崎・三野町大見・高瀬町羽方・山本町神田・財田町財田上です。
しかし、多度津藩は、藩主が丸亀城内に屋敷を構えて居住し、領地には重臣をおいて藩政を任せるという中途半端な存在でした。このような状態から脱し、藩独自の決定を行えるようにするため、多度津藩第四代藩主京極高賢(たかかた)は、多度津に陣屋を建設します。文政10年(1827)に竣工したこの陣屋は、現在のJR四国多度津工場を中心とした辺りにあり、東西約700m、南北約200mにわたり、北は海、南と西は桜川、東は堀で囲まれていました。中には、居館・調練場・武具庫・太鼓楼・藩校・剣術道場・射場などが配置されていましたが、城はありませんでした。西讃辺りでは、この“城が無い”ことを揶揄して、“後(うしろ)が無い”に語呂を合わせて、絶壁頭の人を“多度津の殿さん”という言葉が残っています。
多度津藩は城を築造しなかったものの、第五代藩主高琢(たかてる)の時、それまでの桜川河口の港に替えて、多度津山北側の海に湛浦(たんほ)(港)を建設します。天保9年(1838)に竣工したこの港は大きくて水深が深いため大型船の出入りができ、多くの金毘羅船や北前船が寄港し、多度津は瀬戸内海屈指の港町として発展していきます。明治22年県下で初めて多度津から鉄道が開通したのも、この港があったからです。
武家屋敷のあった家中(かちゅう)の街を訪れると、侍が闊歩する姿を想像することができるかもしれません。
歴史ライター 村井 眞明さん
- 多度津町出身。丸亀高校、京都大学卒業後、香川県庁へ入庁。都市計画や観光振興などに携わり、観光交流局長を務めた。
- 写真

歴史ライター 村井 眞明さん
おすすめ記事
-
2023.06.01

美濃から来讃した生駒氏
シリーズ 中世の讃岐武士(34)
-
2023.04.20

九州で島津軍と戦った讃岐武士
シリーズ 中世の讃岐武士(33)
-
2023.03.02

秀吉軍と戦った讃岐武士
シリーズ 中世の讃岐武士(32)
-
2023.02.02

土佐武士の讃岐侵攻⑥(東讃侵攻)
シリーズ 中世の讃岐武士(31)
-
2022.12.15

土佐武士の讃岐侵攻⑤(十河城包囲)
シリーズ 中世の讃岐武士(30)
-
2022.11.03

土佐武士の讃岐侵攻④(香西氏の降伏)
シリーズ 中世の讃岐武士(29)
-
2022.10.06

土佐武士の讃岐侵攻③(中讃侵攻)
中世の讃岐武士(28)
-
2022.03.17

イリコの島に残る戦国秘話
中世の讃岐武士(23)
-
2022.02.17

三好の畿内奪還の戦いで信長軍と対峙した讃岐武士
中世の讃岐武士(22)
-
2021.12.16

讃岐を支配した阿波の三好氏
中世の讃岐武士(20)
-
2021.11.18

東讃から始まった讃岐の戦国時代
中世の讃岐武士(19)