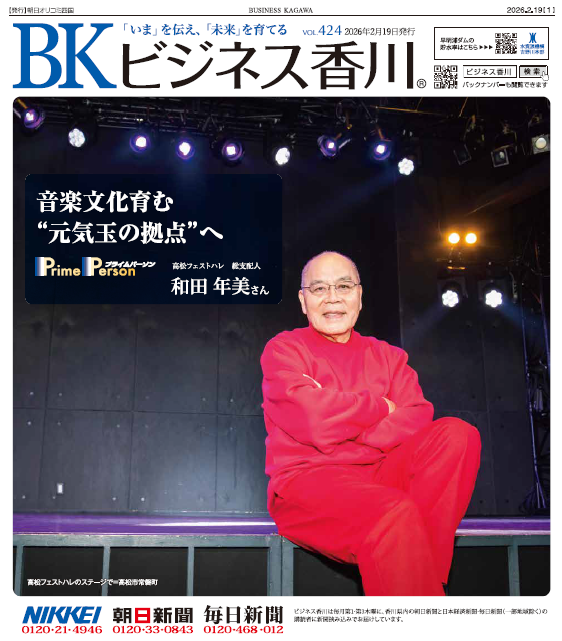奈良県ゆかりの有志で寄贈したお遍路道の石柱
奈良時代の僧侶・行基は、数々の社会事業を通じて民衆に広く慕われ、東大寺の大仏の建立にも尽力した高僧として名高い。近鉄奈良駅前の「行基像」は、待ち合わせ場所の定番である。私も毎日、行基像を見ながら通学していたのだが、その行基が讃岐の地でも活躍していたことは、恥ずかしながら、高松に転勤するまで全く知らなかった。地元の方はよくご存じの通り、行基は、長尾寺や大窪寺をはじめ様々な寺を創建したほか、塩江温泉を開くなど、多くの足跡を残している。また、改めて歴史を紐解いてみると、行基に限らず、古くから栄えた讃岐と奈良の間には、驚くほど多くの人々の往来がある。例えば、「令和」で改めて注目の万葉集を代表する歌人、柿本人麻呂は、讃岐でいくつかの歌を詠じている。沙弥島で詠んだと伝えられる「玉藻よし讃岐の国は」で始まる長歌は、特に有名である。
こうした先人達にあやかってという訳でもないが、先日、奈良に縁のある香川県在住の有志十数名で、お遍路道の石柱を寄贈した。縁あってお世話になっている香川に対するささやかなお礼の気持ちである。石柱は、三豊市の本山寺(70番札所)と弥谷寺(71番札所、この寺も行基による建立とのこと!)の間に設置された。大変有難いことに、若いご夫婦が最近始められたモダンな遍路宿の脇の土地をご提供頂いた。七宝山を臨むのどかな遍路道に立つと、讃岐と奈良の悠久の歴史ロマンを感じずにはいられない。
サラリーマンは、勤務地を自分で選ぶことはできないが、人生には、行く先々で不思議な縁がある。香川には、特に地縁・血縁はなかったのだが、この地で多くの魅力的な人々と出会い、素晴らしい時間を過ごすことが出来るのも、もしかしたら、行基菩薩のお導きなのかもしれない。
日本銀行高松支店長 正木 一博
- 写真

おすすめ記事
-
2019.04.04

瀬戸内国際芸術祭への期待
日本銀行高松支店長 正木 一博
-
2019.01.17

お年玉と金融教育
日本銀行高松支店長 正木 一博
-
2018.10.18

現金大国のキャッシュレス化
日本銀行高松支店長 正木一博
-
2017.11.02

ネット社会と地方都市の未来
日本銀行高松支店長 正木 一博
-
2017.08.03

連絡船と瀬戸大橋
日本銀行高松支店長 正木 一博
-
2018.07.19

香川県の企業の「底力」
日本銀行高松支店長 正木 一博
-
2018.05.03

日銀 vs 仮想通貨
日本銀行高松支店長 正木 一博
-
2018.02.01

「恵方巻」と「あん餅雑煮」
日本銀行 高松支店長 正木 一博
-
2025.06.19

備讃瀬戸と讃岐平野の造形美
香川大学特任教授・讃岐ジオパーク構想推進準備委員会委員長 長谷川修一
-
2023.04.06

お城の楽しさ
日本銀行 高松支店長 高田 英樹
-
2022.08.04

魅力をもっと伝えるために
日本銀行 高松支店長 高田秀樹