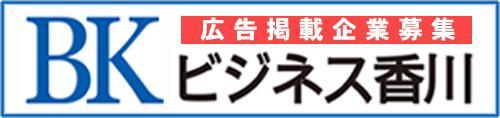三豊市三野町下高瀬にある高永山本門寺
弘安年間(1278~88年)、秋山光季(みつすえ)は、幕府の命によって、孫の泰忠ら一族を引き連れて讃岐国へ移住し、三野郡高瀬郷(現・三豊市高瀬町)に居を構えます。そのとき、甲斐国に在住していた頃秋山氏は一族のほとんどが日蓮宗に帰依していたことから、日蓮六老僧の一人・日興にその弟子の日華(にっけ)を導師として讃岐に派遣するよう懇願します。しかし日華が病気のためそのおとうと弟子の日仙が派遣され、那珂郡柞原郷田村(現・丸亀市田村町)に法華堂を建立します。現在の番神宮がその旧跡だといわれています。しかし、折り悪くも田村の拠点が争乱に巻き込まれて灰燼(かいじん)に帰したため、泰忠は高瀬郷内の地を寄進し、再び日仙を迎えて正中2年(1325)に今の高永山本門寺を氏寺として建立します。その後本門寺では文安3年(1446)までの100年間に末寺6カ寺ができ、本門はこれら六坊に対して大坊と呼ばれました(高瀬大坊)。
京都における日蓮宗のはじめての布教活動は、永仁元年(1293)、日蓮の弟子の日像が京都へ入りしたときといわれています。讃岐は弘法大師空海をはじめ五大師を輩出し、古くから仏教の盛んなところですが、このような地に、東国生まれの新興仏教であった日蓮宗が、当時日本の中心であった京都よりも早く弘安年間に伝わっていたというのは非常に興味深い出来事です。
村井 眞明
歴史ライター 村井 眞明さん
- 多度津町出身。丸亀高校、京都大学卒業後、香川県庁へ入庁。都市計画や観光振興などに携わり、観光交流局長を務めた。
- 写真

歴史ライター 村井 眞明さん
おすすめ記事
-
2023.06.01

美濃から来讃した生駒氏
シリーズ 中世の讃岐武士(34)
-
2023.04.20

九州で島津軍と戦った讃岐武士
シリーズ 中世の讃岐武士(33)
-
2023.03.02

秀吉軍と戦った讃岐武士
シリーズ 中世の讃岐武士(32)
-
2023.02.02

土佐武士の讃岐侵攻⑥(東讃侵攻)
シリーズ 中世の讃岐武士(31)
-
2022.12.15

土佐武士の讃岐侵攻⑤(十河城包囲)
シリーズ 中世の讃岐武士(30)
-
2022.11.03

土佐武士の讃岐侵攻④(香西氏の降伏)
シリーズ 中世の讃岐武士(29)
-
2022.10.06

土佐武士の讃岐侵攻③(中讃侵攻)
中世の讃岐武士(28)
-
2022.03.17

イリコの島に残る戦国秘話
中世の讃岐武士(23)
-
2022.02.17

三好の畿内奪還の戦いで信長軍と対峙した讃岐武士
中世の讃岐武士(22)
-
2021.12.16

讃岐を支配した阿波の三好氏
中世の讃岐武士(20)
-
2021.11.18

東讃から始まった讃岐の戦国時代
中世の讃岐武士(19)