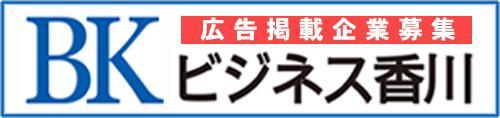「プリンター用は世界シェアの80%。ライバルはありません。ファクス用は50%ぐらい。お客さんの要望に応じてコツコツやっていたら、いつの間にかこうなりました」・・・・・・大矢根利器製作所8代目社長の大矢根裕一さん(63)は淡々と語る。
1898年(明治31年)に創業、たばこナイフで基盤を築いた。金切り鋸刃(のこば)やペンチ、そして製紙工業用刃物へ。ミニラボ用(写真印画紙)から、ファクスやコピー機、プリンターなどOA機器用カッターへ。成長の秘密は、市場の変化を見据えて商機を逃さなかったことだ。
刀鍛冶の技術
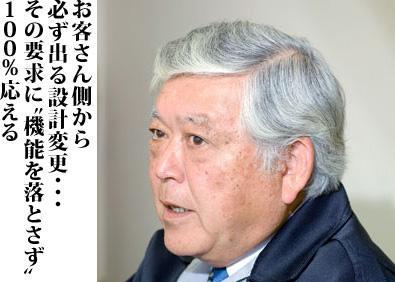
「侵炭(しんたん)法でたばこ葉のきざみ包丁を作ったんです。たばこが1904年(明治37年)の煙草専売法で国有化され、日本専売公社から納入指名を受けて事業が拡大しました」
33年、金切鋸(ハクソー)の製造を始めた。戦後はペンチ、軽量発泡コンクリート用鋸など、製品は時代のニーズに応じて変わった。
「金切鋸刃は、東京だけでも販売店が二十数社ありました。ペンチは新潟のメーカーとの競合で、採算が合わなくなってやめました。コンクリート用鋸は、業界の不況で売り上げが減っています」
隣町の川之江(現四国中央市)や伊予三島(同)に製紙企業が多いため、トイレットペーパーやティッシュ製造用刃物も開発した。
※侵炭法
炭素の含有量が多いと硬くなる鉄の性質を利用する、古くからの製法。炭材を塗った鉄を高熱処理して、鉄の表面層を高炭素鋼にする。
※軽量発泡コンクリート
気泡を混入したコンクリート。
刃物のユニット化
70年代後半、それに代わって普通紙を使うPPCコピー機が登場して、ロール紙を使う感熱記録方式のファクスの生産が始まった。
「単体部品だったカッターを、小型化、軽量化してファクスのユニット製品にしました。松下電送システムさんから始まって、日本のほとんどの電機メーカーに納入しました」。カッターユニットは月産数百台からスタートして、最盛期は20万台になった。
DPEやミニラボ用も手がけた。「紙が厚い印画紙は切りにくいんです。切れ味を良くするのは難しい技術ですが、8~9割のシェアを持っていました」
ファクス用の需要は、しばらくして減った。普通紙を使うプリンター複合機が普及したからだ。DPEやミニラボ用も、カメラのデジタル化で銀塩写真の市場が縮小した。
市場の変化に応えて、レジスターや券売機用のカッターユニットに力を入れた。
「ノコギリ状の刃で、びりっと手で1枚ずつ切り離していたレシートやチケットを、顧客の要求で、自動式で速くきれいに切れるようにしました」
カッターは、刃を上からおろして切るギロチン式や、円盤の刃を回転させるピザカッターなど、用途に応じていろいろある。基本ははさみと同じ、刃を交錯させて切る技術だ。
需要の変化に対応できたのは、刃物を、精密、軽量、小型化でユニット化して製品にした開発力だ。さらに、高品質、低コスト、短期納入の差別化が商品力を高めた。
※青焼き
ジアゾ式複写技法。光の明暗が青色の濃淡として写るためこう呼ばれる。
※松下電送システム
現パナソニック コミュニケーションズ株式会社
※PPCコピー機
1938年にアメリカのチェスター・F・カールソンが基本技術を発明。ハロイド社(現ゼロックス)が買い取って、1959年に開発した事務用複写機。
※DPE・ミニラボ
フィルムの現像、焼き付け、引き伸ばしを行う店舗や小型機械の総称。
※銀塩写真
フィルムを利用する写真。
※プリンター複合機
プリンターにスキャナーやファクスなどの機能を備えた製品。
ライバルは大企業
悔しい思いをして多くを学んだ。「特許申請さえしておけば、わが社の技術だと証明されるので、分かり切ったことでも防御のために申請するようにしました」
品質管理も一流企業と同じレベルを目指した。人材も知識も無かった。「恥を忍んで、お客さんに初歩から教えてもらい、十数年前にISO9001と14001を取得しました。教えてもらったことで、お客さんと共に開発する企業風土が根付いたように思います」。大矢根さんは胸を張った。
※ISO9001・14001
国際標準化機構(International Organization for Standardization)。略称ISOは、電気分野を除く工業分野の国際規格を策定するための民間の非政府組織。9001は品質マネジメントシステム規格。14001は環境マネジメントシステムに関する国際規格(IS)の総称。
大手にできないことを
「まず最初に、要求される機能とコストを満たすものを作ります。しかし、切る素材や耐久性、サイズなど設計変更が必ずお客さん側から出ます。その要求を、機能を落とさず100%クリアする物を次に作るんです」
大企業の営業スタイルは、納入する部品に合うように、お客さんの設計を変えてもらう場合が多い。「それでは部品供給側のエゴになります。ですから、お客さんの要望に沿って一緒にアイデアを出し合って開発するんです」
ニーズにとことん応える努力と能力・・・・・・それが大手に負けない最大の強みだ。
113年の歴史と経験
大矢根さんが子供のころ、熱処理場には暗幕を張っていた。「加熱した鉄の微妙な色を見て、一つずつ焼き入れをしていました。そうするとひずみが少ないんです」
今は、機械の温度と時間をセットすれば、同じ硬度の刃物が大量生産できる。しかし機械には限界がある。「鉄を焼き入れする真空炉は、窒素ガスを吹き付けて鉄を冷却します。ガスの当たる角度や位置によって冷え方が違い、ひずみが出るんです」
機械の精度が良くなって、難しい工程が楽になった。「機械が勝手に加工してくれるようになって、人間の能力のほうが少しずつ退化してきたように思います」
113年蓄積してきた刃物の知識。言葉で伝えにくい焼き入れや研磨技術を、若い人たちに教えるのは、機械の進歩でかえって難しくなったとも思う。大矢根さんの課題でもある。
113年の、もっと先へ

手すりや介護用の機器などを造る(株)シコクとの共同開発で、6月から中国の工場で生産が始まる。市場は広い。介護、公共施設や列車、高速道路のサービスエリア、デパートなどには介護用トイレが必ずある。
大矢根さんは、もっと大きな市場にも目を向けている。日本では買い物で受け取るレシートも、飛行機や電車、バスのチケットも、レジスターや券売機のカッターユニットで発行される。
「中国やインドはこれからOA機器が普及します。それに組み込まれるわが社の刃物は、月産数百万台の展開が期待できます」・・・・・・目が輝いている。
中国進出に懸念なし
技術流出の恐れはないという。「我々の製品は機能部品です。形だけまねてもダメです。最初の10カットは良く切れても、100万カット、200万カット同じ切れ味が続かないとダメなんです。中国企業の価格より我々が高くても、品質でそれなりの利益を出しながら、やって行けると思います」
切れ味と耐久力で信用を積み上げてきた歴史が、自信を支える。
大矢根 裕一 | おおやね ゆういち
- 1948年 三豊郡仁尾町生まれ
1967年 日本大学商学部卒業
1971年 千代田精機入社
1977年 大矢根利器製作所入社
1997年 代表取締役就任
現在に至る
- 写真

株式会社大矢根利器製作所
- 所在地
- 三豊市仁尾町丁396
TEL 0875-82-3101 /FAX 0875-82-4326 - 設立
- 1898年
- 代表者
- 代表取締役 大矢根 裕一
- 資本金
- 6000万円
- 従業員
- 112名
- 事業内容
- 〈工業用刃物〉小型プリンター用カッターユニット、OA機器用ペーパーカッターユニット、発券機シートカッターユニット、ラボシステム用各種刃物、化学工業用刃物、紙工業用刃物、たばこ製造用刃物、食品加工用刃物
〈精密加工品〉測定器用部品、OA機器用部品、油圧機器用部品
〈鋸刃〉手引き用、機械用、塩ビ用、ALC用等 - 沿革
- 1898年 安政元冶年間の剣工祐廣の技術を継承し、たばこナイフ製作専業で基盤を築き、専売局創設と共に納入指名を受け大矢根兄弟合資会社を設立
1915年 中国上海市に朝日煙刀経售慮を開設
たばこナイフの輸出開始
1933年 ハクソーの製造開始
1953年 ペンチの製造開始
1956年 株式会社大矢根利器製作所に組織変更
1976年 資本金6000万円に増資
1980年 東京営業所開設
1987年 台湾新竹県に合弁会社大亜精密製刀股份有限公司を設立
1991年 大阪営業所開設
1998年 創業100周年
2009年 中国広東省珠海市にORC珠海有限公司を設立
- 確認日
- 2018.01.04
おすすめ記事
-
2011.03.17

チャレンジが「口福」(こうふく)を呼ぶ!
和田精密歯研 会長 和田 弘毅さん
-
2017.07.20

高い吸湿能力を追求した 工業用乾燥剤
株式会社レクザム SUNDRY-Ⅱ
-
2026.02.05

デジタルとアナログの融合で「麺のエキスパート」へ
まるみやホールディングス 社長 宮谷 和宗さん
-
2026.01.01

“移動”を支えるプラットフォーマーへ
トヨタカローラ香川 社長 向井 良太郎さん
-
2025.12.18

“現場知る強み”活かし 地域・お客さまを元気に
香川銀行 頭取 有木 浩さん
-
2025.12.04

財産は「人」。安全・安心・快適を届ける
西日本高速道路エンジニアリング四国
社長 後藤 由成さん -
2025.11.06

“ケタ違い”のものづくりで世界の物流を支える
マキタ 社長 槙田 裕さん
-
2025.10.16

次世代を支える担い手づくりへ
JA香川県 代表理事 理事長
北岡 泰志さん -
2025.10.02

暮らしや人生にそっと寄り添って
生活協同組合 コープかがわ
代表理事 理事長 亀井 愛知さん -
2025.09.04

企業や暮らしを「システム」で支える
ロジック 社長 山﨑 直樹さん
-
2025.08.21

「ここに来て良かった」 生徒一人一人に寄り添って
学校法人村上学園 理事長
村上学園高等学校 校長
村上 太さん