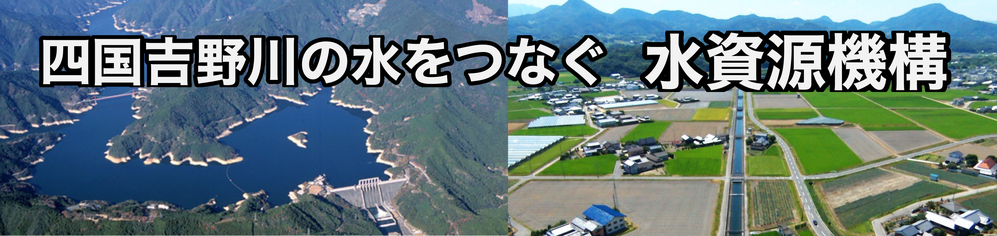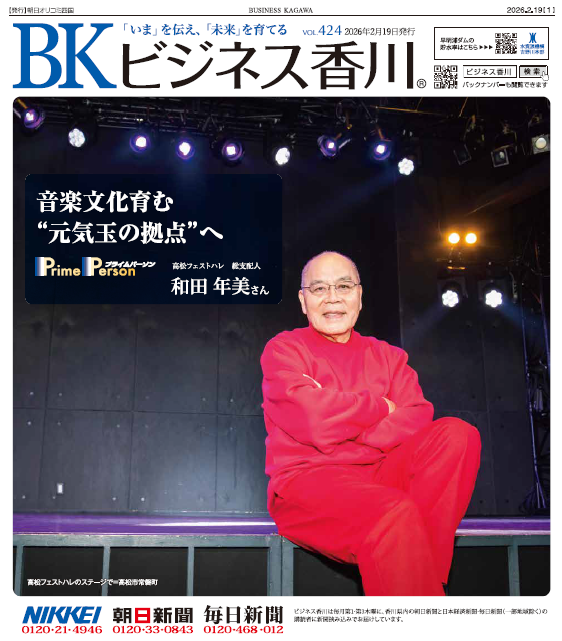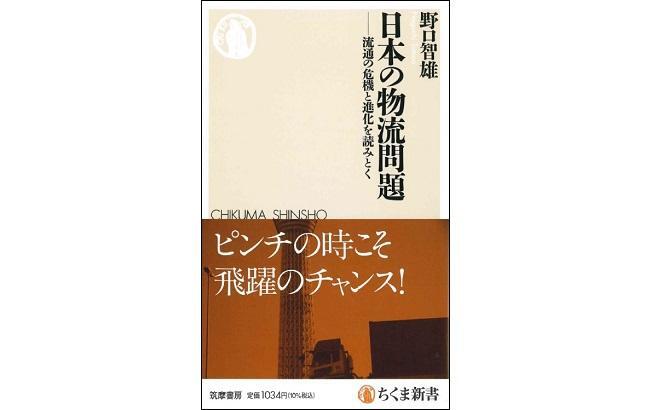
著者によると、宅配便の取扱個数は2022年についに50億個の大台を超え、2000年比で実に95.4%増加したということです。一方で個数ではなく量、つまり積載量に輸送距離をかけた国内貨物の輸送量はどうなっているかといいますと、同期間比で逆に27.5%減になっているそうです。またトラックに積む貨物の積載率の変化は2000年の43.7%から2022年は36.5%へと大きく低下しています。トラックの荷台の中身は荷物が4割弱、6割あまりは空気を運んでいるなどと揶揄されており、効率面でも経年劣化が進んでいると述べます。もちろん積載率の改善は必要ですが、著者はこの数字の奥にこそ物流の現代化を阻害する真の災厄が潜んでいるといいます。
2024問題で物流業界には大きなスポットライトが当たっていますが、それは変わるための大きなチャンスでもあるということでもあり、それをどのような方法で乗り切るかを著者はAI物流、ドローン配送、ロボット化、自動運転など今起こっている様々な技術変革の波を説明しています。概説書としてとても分かりやすく書かれた本だと思います。一方で消費者の立場から見ると、運賃の値上げや宅配便の再配達の有料化の動きが出てきていますが、賛成や反対以前に街なかで宅配業の人たちの忙しそうな姿を見るにつけ、誰かの犠牲の上に立って、あまり急いでいない荷物をそんなに速くせかして配達してもらう意味はあるのかなとも思ってしまいます。
宮脇書店 総本店 店長 山下 郁夫
宮脇書店 総本店店長 山下 郁夫さん
- 坂出市出身。約40年書籍の販売に携わってきた、
宮脇書店グループの中で誰よりも本を知るカリスマ店長が
珠玉の一冊をご紹介します。 - 写真

宮脇書店 総本店店長 山下 郁夫さん
おすすめ記事
-
2025.01.03
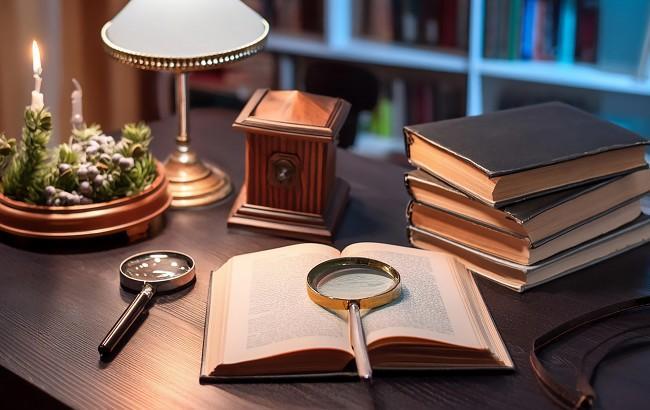
いつも、そばに
宮脇書店 総本店店長 山下 郁夫
-
2024.12.19
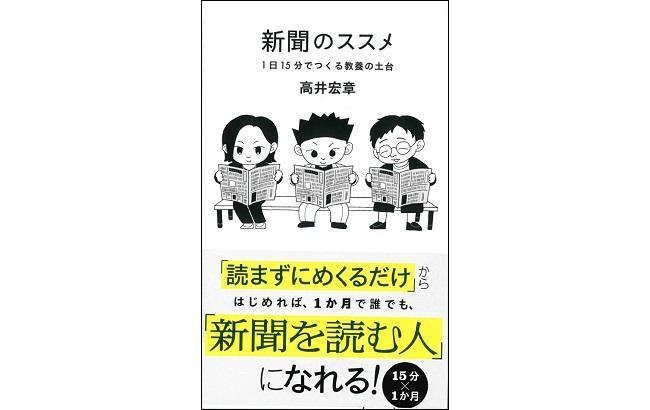
新聞のススメ
1日15分でつくる教養の土台著:高井 宏章/星海社
-
2024.10.17
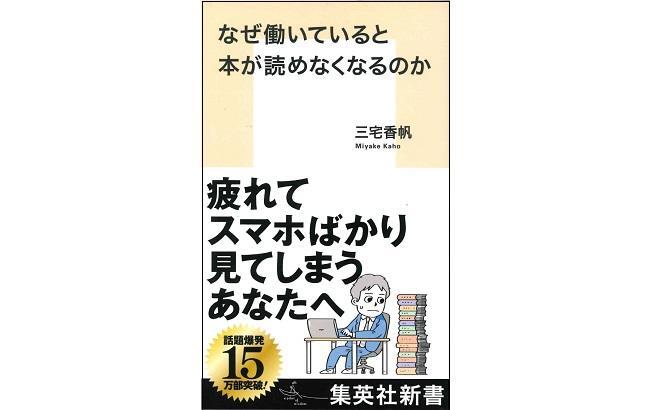
なぜ働いていると本が読めなくなるのか
著:三宅 香帆/集英社
-
2024.08.01
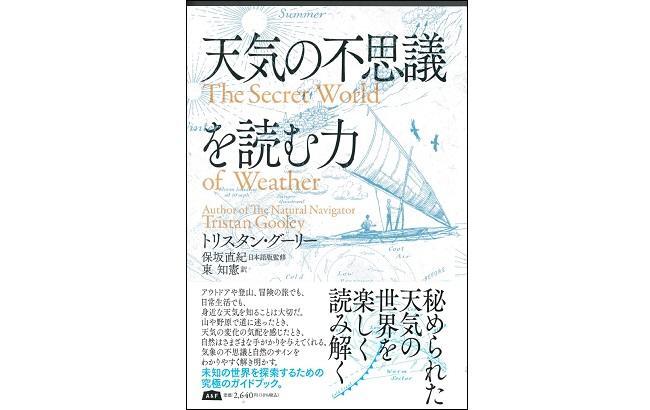
天気の不思議を読む力
著:トリスタン・グーリー/エイアンドエフ
-
2024.07.04
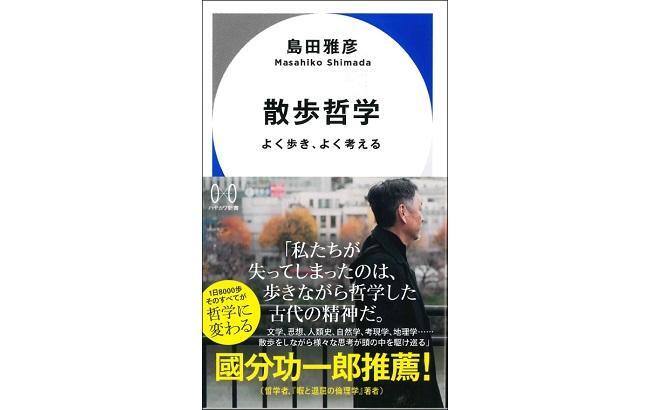
散歩哲学 よく歩き、よく考える
著:島田 雅彦/早川書房
-
2024.01.04
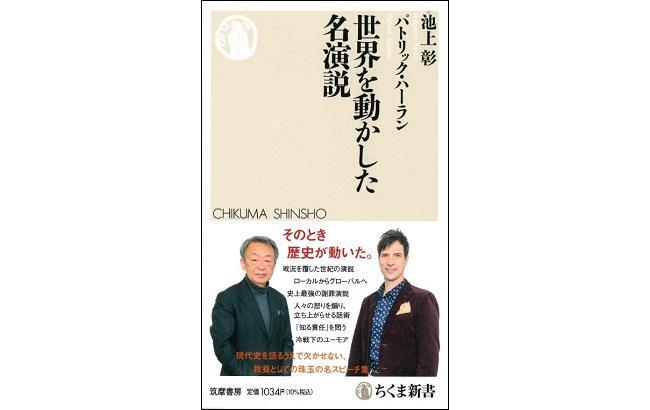
世界を動かした名演説
著:池上 彰、パトリック・ハーラン/筑摩書房
-
2023.12.07
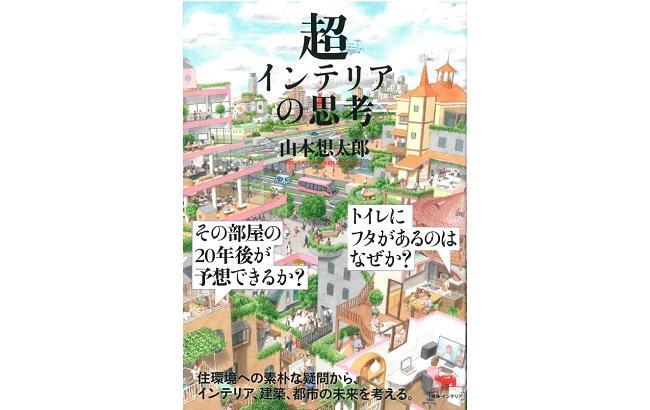
超インテリアの思考
著:山本 想太郎/晶文社
-
2023.11.02
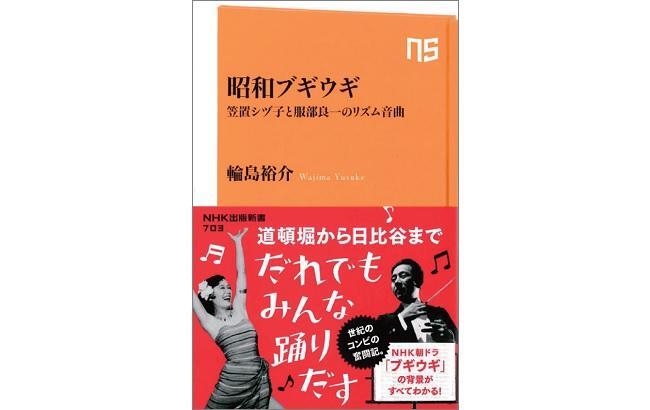
昭和ブギウギ
笠置シヅ子と服部良一のリズム音曲著:輪島 裕介/NHK出版
-
2023.10.05
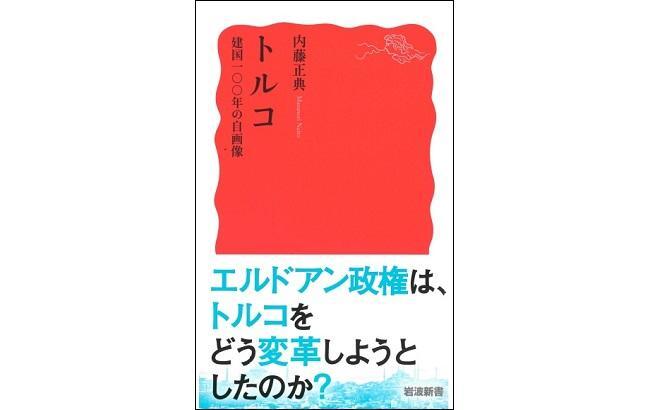
トルコ 建国一〇〇年の自画像
著:内藤 正典/岩波書店
-
2023.09.07
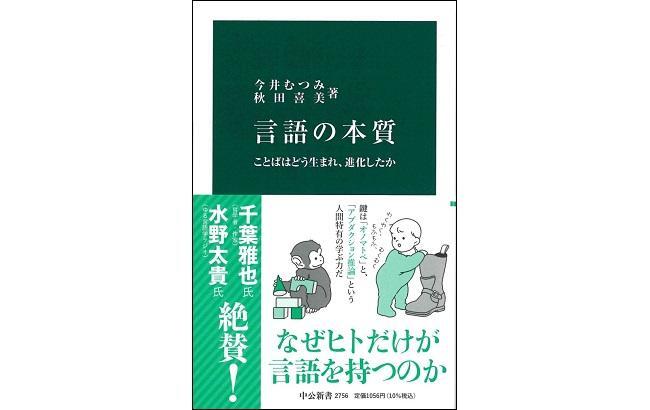
言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか
著:今井 むつみ、秋田 喜美/中央公論新社
-
2023.08.03
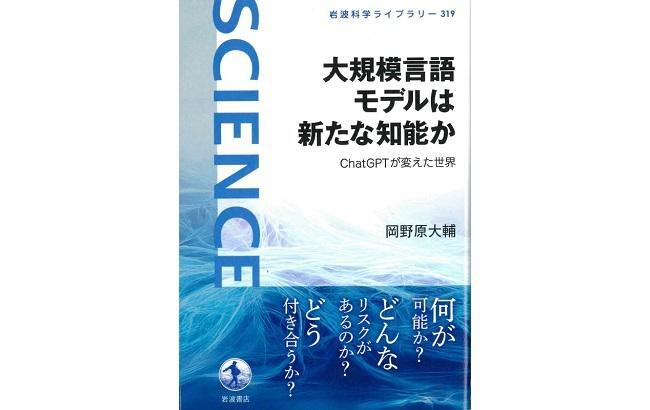
大規模言語モデルは新たな知能か ChatGPTが変えた世界
著:岡野原 大輔/岩波書店