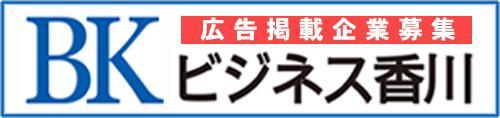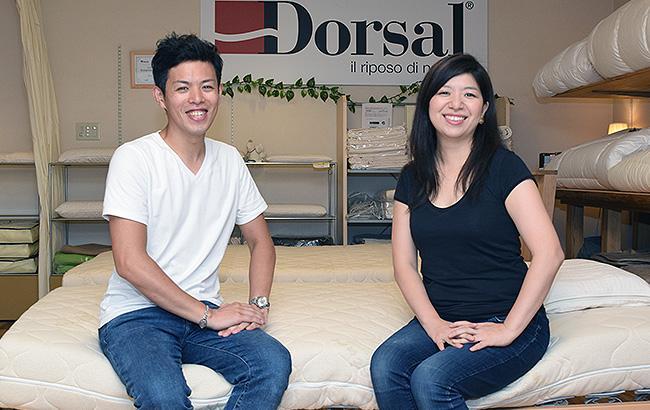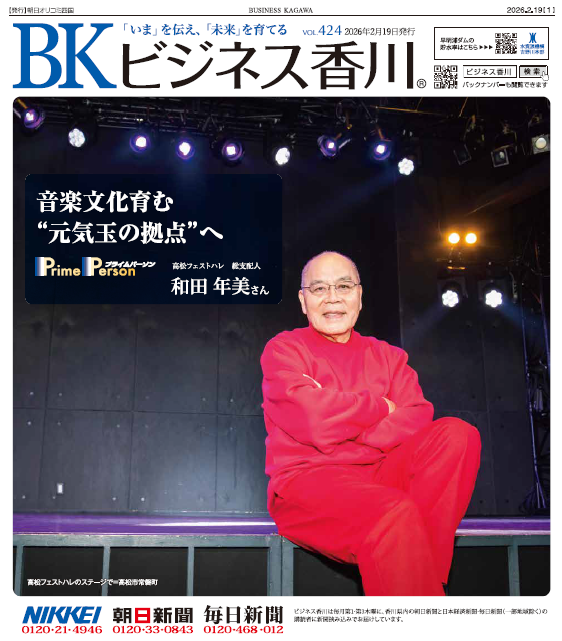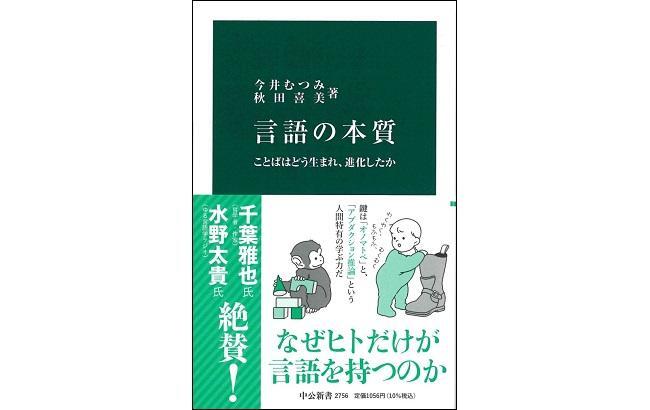
今回紹介する本では、コミュニケーションのための大切な道具であり、ものを考えることや芸術の源でもある「ことば」はどう生まれ、進化したのか、そしてなぜ人だけが言語を持つのかを著者の認知科学者と言語学者の二人がその探求の旅に連れていきます。巨大なシステムである言語の起源やヒトとAIや動物との違い、言語の本質を問うことは、人間とは何かを考えることであり、その鍵は、「オノマトペ」と「アブダクション(仮説形成)推論」という人間特有の学ぶ力だと著者は述べます。赤ちゃんがことばを覚える過程は、まず「もぐもぐ」とか「ふわふわ」などのオノマトペからです。そこからどうやって赤ちゃんは巨大なシステムである言語というものを獲得していくのでしょうか。ことばというものは非常に複雑で、ヒトがそれを獲得していくメカニズムには、まだ解明できないことがたくさんあるようです。
認知科学では「記号接地問題」という未解決の大きな問題があるそうです。この本ではメロンを例にあげて、メロンを食べたことがあれば、メロンということばを聞くだけで色やにおい、味、舌触りなどの特徴を思い出すことが出来ますが、食べたことのない果物の場合はどうでしょう。つまり言語というものは、本当に身体から独立した記号として理解したり話したりすることが出来るのか、そしてコンピュータにことばの本当の意味が分かるのか、という疑問がわいてきたといいます。スペースがないので詳しく書けませんが、一方で近年のAIの発達によって、言語学も変革を迫られており、これまで不可能だったことが着実に実行されていくという意見もあります。
言語というものは、国や民族、その地域の歴史や文化がつくり上げていくものですが、AIというものは、人がつくり上げてきたこれまでの言語と全く違ったものを、つくってしまう可能性はあるのでしょうか。
山下 郁夫
宮脇書店 総本店店長 山下 郁夫さん
- 坂出市出身。約40年書籍の販売に携わってきた、
宮脇書店グループの中で誰よりも本を知るカリスマ店長が
珠玉の一冊をご紹介します。 - 写真

宮脇書店 総本店店長 山下 郁夫さん
おすすめ記事
-
2020.10.01
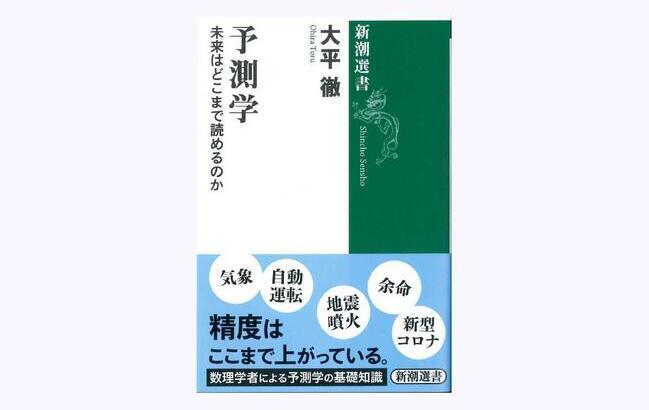
予測学
著:大平 徹/新潮社
-
2019.07.04
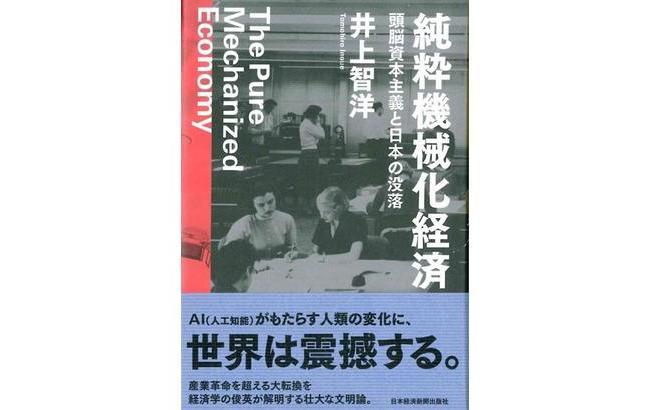
純粋機械化経済 -頭脳資本主義と日本の没落-
著 井上智洋/日本経済新聞出版社
-
2025.01.03
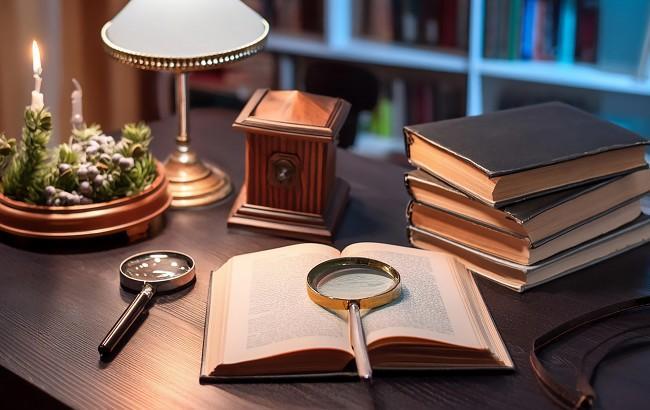
いつも、そばに
宮脇書店 総本店店長 山下 郁夫
-
2024.12.19
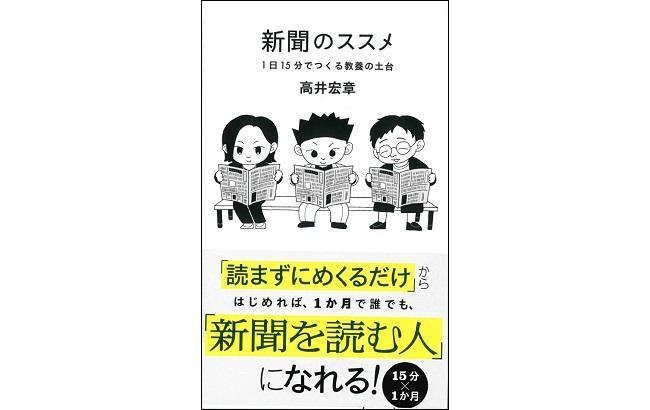
新聞のススメ
1日15分でつくる教養の土台著:高井 宏章/星海社
-
2024.10.17
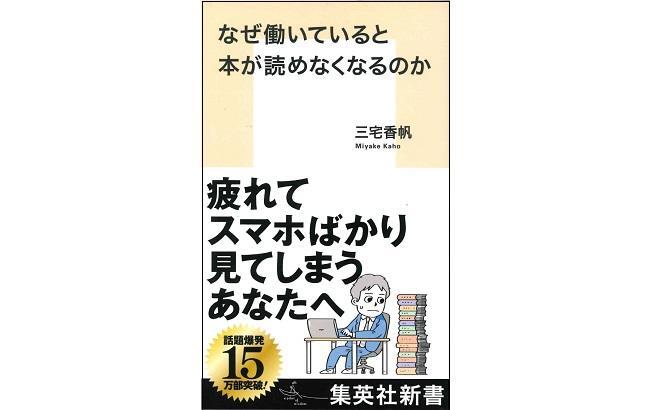
なぜ働いていると本が読めなくなるのか
著:三宅 香帆/集英社
-
2024.08.01
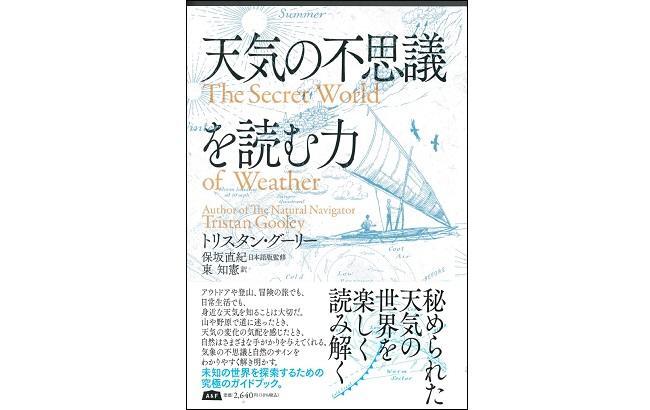
天気の不思議を読む力
著:トリスタン・グーリー/エイアンドエフ
-
2024.07.04
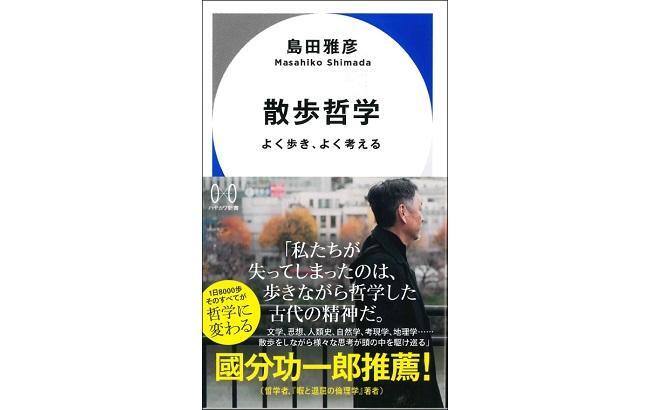
散歩哲学 よく歩き、よく考える
著:島田 雅彦/早川書房
-
2024.06.06
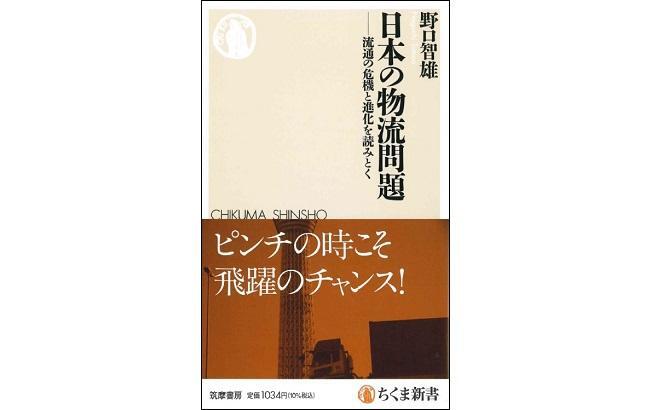
日本の物流問題-流通の危機と進化を読みとく
著:野口 智雄/筑摩書房
-
2024.01.04
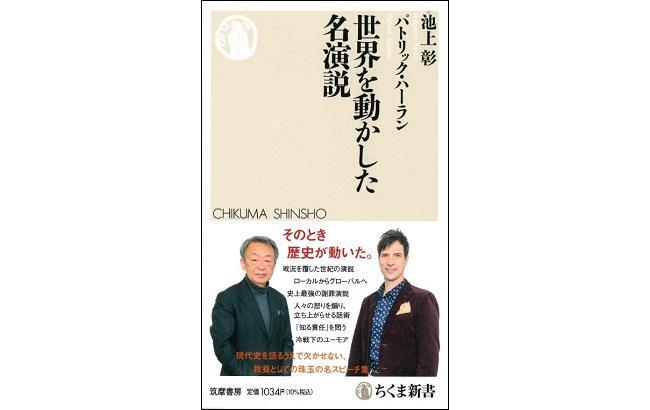
世界を動かした名演説
著:池上 彰、パトリック・ハーラン/筑摩書房
-
2023.12.07
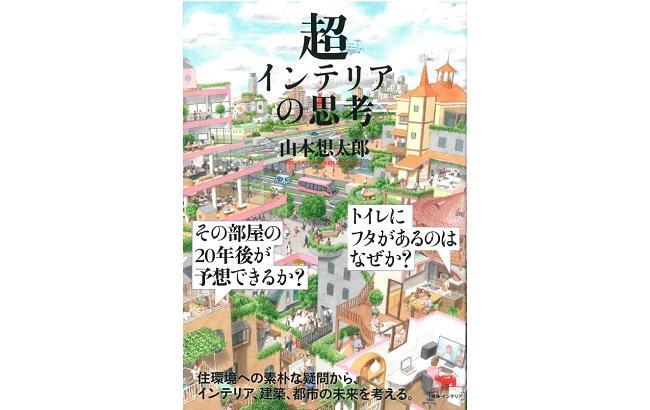
超インテリアの思考
著:山本 想太郎/晶文社
-
2023.11.02
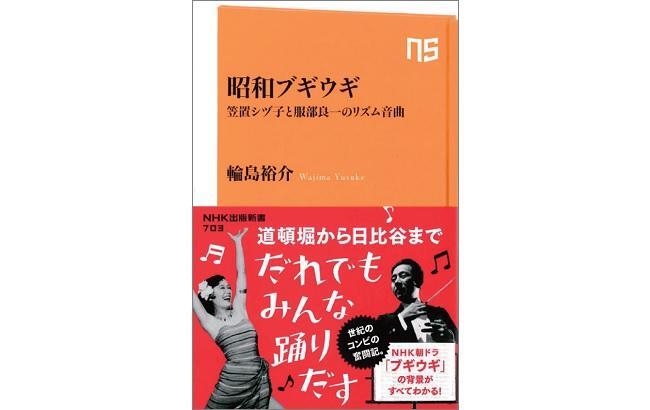
昭和ブギウギ
笠置シヅ子と服部良一のリズム音曲著:輪島 裕介/NHK出版