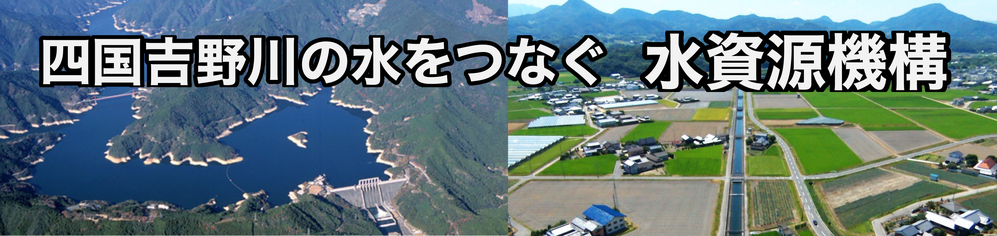屋島・長崎の鼻
このように海防の危機が迫る中、高松藩主松平頼聰(よりとし)(11代)も幕府の命を受け、同年7月、屋島北端の長崎の鼻に砲台を設置します。設計・鋳造したのは藤川三渓(さんけい)で、若き日に長崎で医学のほか、高島秋帆(しゅうはん)の下、西洋砲術をはじめ洋式兵学、大砲鋳造、捕鯨の技術を学んでいました。三渓はこの大砲を震遠(しんえん)砲と名付け、砲身に自作の漢詩を彫刻しています。また、農民545名からなる竜虎隊を結成し、自ら隊長となって洋式訓練を施します。
三渓は、長崎遊学から高松に戻った後、江戸・京へ出たときに勤王の志士らと交わってその思想に共鳴したといいます。再帰藩した彼は、頼聰の伯父で高松藩勤王派の首魁・松平左近(諱(いみな)は頼該(よりかね)、号は金岳)の片腕として活躍し、屋島の砲台もそのとき造ったものです。しかし、その積極的な行動は藩内佐幕派の反感をかい、文久3年8月18日に起きた会津藩・薩摩藩を中心とした公武合体派が、長州藩ら尊皇攘夷派と急進派公卿を京都から追放した事件を契機に、三渓は高松藩内で失脚し、6年間、鶴屋町の獄に繋がれます。
その後、戊辰戦争が始まると三渓は出獄し、新政府の奥羽征討軍に加わり、また官吏を務めます。しかし、明治14年に下野し、我が国で初めて捕鯨の事業化を試み、東京や大阪に水産学校を創立するなど水産業に身を捧げ、日本近代水産業の開拓者といわれています。
三渓の出身地の高松市三谷町にある三渓小学校は、その名前からつけられたものです。また、多度津高等学校には三渓に関する資料が保存されています。
次回(9月20日号)は、文久3年8月17日の天誅組蜂起の時の話です。
歴史ライター 村井 眞明さん
- 多度津町出身。丸亀高校、京都大学卒業後、香川県庁へ入庁。都市計画や観光振興などに携わり、観光交流局長を務めた。
- 写真

歴史ライター 村井 眞明さん
おすすめ記事
-
2023.06.01

美濃から来讃した生駒氏
シリーズ 中世の讃岐武士(34)
-
2023.04.20

九州で島津軍と戦った讃岐武士
シリーズ 中世の讃岐武士(33)
-
2023.03.02

秀吉軍と戦った讃岐武士
シリーズ 中世の讃岐武士(32)
-
2023.02.02

土佐武士の讃岐侵攻⑥(東讃侵攻)
シリーズ 中世の讃岐武士(31)
-
2022.12.15

土佐武士の讃岐侵攻⑤(十河城包囲)
シリーズ 中世の讃岐武士(30)
-
2022.11.03

土佐武士の讃岐侵攻④(香西氏の降伏)
シリーズ 中世の讃岐武士(29)
-
2022.10.06

土佐武士の讃岐侵攻③(中讃侵攻)
中世の讃岐武士(28)
-
2022.03.17

イリコの島に残る戦国秘話
中世の讃岐武士(23)
-
2022.02.17

三好の畿内奪還の戦いで信長軍と対峙した讃岐武士
中世の讃岐武士(22)
-
2021.12.16

讃岐を支配した阿波の三好氏
中世の讃岐武士(20)
-
2021.11.18

東讃から始まった讃岐の戦国時代
中世の讃岐武士(19)