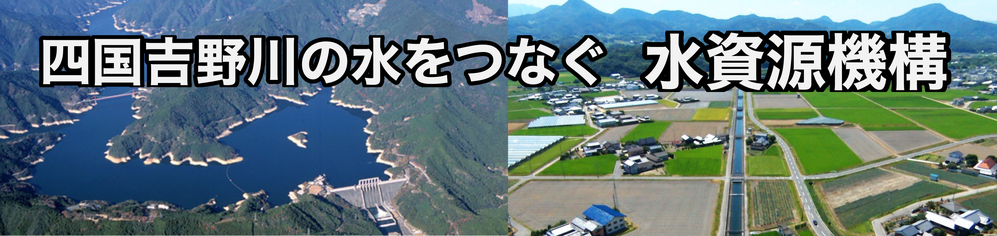日本のオリーブ栽培は、1908年に小豆島で始まった。栽培面積のピークは64年の120ヘクタール(豊島を含む)だったが、80年代後半、安い外国製品と、農薬エンドリンの禁止による害虫被害で、農家が生産意欲を失い約30ヘクタールまで減少した。
醤油も佃煮も素麺も、原料は島でつくれない。「でも、島には他の地域にない大事な資源がある。オリーブだ」。89年から無農薬農法で栽培を始めていた植松さんの目標は、新しい「本場の本物」づくりだった。
※エンドリン
1954年、農薬登録を受けた。野菜のアオムシやアブラムシ、カメムシ、果樹のハマキムシの駆除に使われたが環境に対する影響が大きいため、81年、使用が禁止された。
本場の本物
「納得のいく醤油をつくりたかったんです」。100年を超えて使われてきた杉の大樽を、他の蔵元から譲り受け、伝統の「本場の本物」製法にこだわった。無農薬の国産大豆や小麦、天日製塩で醤油をつくるヤマヒサは、24年前に海外の認証機関でオーガニック認定を受けた。
瀬戸大橋開通もバブル景気も、小豆島は蚊帳(かや)の外だった。観光客は素通りしたし、醤油も佃煮も素麺も売り上げは横ばいだった。植松さんは、他の地域にないオリーブを資源として見直した。
「京阪神や首都圏の取引先から頼まれて、醤油の他に、国産小麦の素麺や無添加の佃煮などを販売していたんです。それなら自社で品質を管理できるオリーブオイルを生産すればいい、そう思ったんです」
※本場の本物
日本各地で伝統的に培われた製法で、地域特有の材料を用いて作り続けているものに与えられる地域食品ブランドの標準基準。財団法人食品産業センターが認定する。
醤油もオリーブと同じ

植松さんは海外の産地を視察して、オリーブも醤油も同じだと確信した。オリーブは雨と湿度を嫌う。
「雨が多かったら、口当たりのやさしいオリーブが出来ます。雨が降らなければ、渋みの強い味になります。醤油も樽ごとの味が違います」
オリーブも醤油も自然の力が味を決める。植松さんは少量良品を頑固(がんこ)に守る。その味は毎年微妙に違う。
無農薬栽培は戦い
農耕用台車にすわって、はいつくばって頭を下げて、一本ずつ木を見上げて虫を探して手でとる。
「5月から9月まで、毎日のように朝5時ごろから昼までかけて虫退治。無農薬栽培はせいぜい50本が限界です」。被害も受けた。体も壊したが、17年間なんとか無農薬農法を続けた。
「オリーブオイル用の木は、減農薬に切り替えました。県の指導では、スミチオンの散布は1年に3回ですが、1回にしています」。フンが付いている木は、ゾウムシが入っているから2回かける。
オリーブオイルはジュース
果物のジュースと同じように、果実をしぼって採油するオリーブオイルはジュースそのものだ。栽培条件や管理状態で味や香りが変わる。
「小豆島産は、輸入品より値段が高いですが新鮮です。秋に収穫したオリーブをしぼって、早いものは年内に売りだします」
オリーブオイルの輸入量は年間4万トン程度、小豆島のオリーブ果実の収穫量は150トン、新漬に半分以上使うので、せいぜい4~5トンが精一杯だ。
「昨年秋の天候不順で、今年は2200本(200ミリリットル)しか採れなかったんです。予約で売り切れました。まとめて20本、30本と買われる人もいるんです」。去年が5千本、一昨年が7200本だった。
葉っぱで商品開発
オリーブ栽培100周年の08年、小豆島町役場に〝オリーブ課〟が出来た。「和歌山県みなべ町にうめ課がありますが、オリーブで地域振興を図りたいという願いが議会で承認されたおかげです」
植松さんは、農園を3.2ヘクタールに拡大した。
「オリーブオイルには効能がいろいろありますが、葉っぱも強い抗酸化効果があることが分かったんです。チャンスです」
北アフリカで、お茶として飲まれていることを知って、オリーブ茶を開発した。ティーバッグと抹茶、ペットボトルのお茶、オリーブ茶石鹸も商品化した。
「普通のお茶は焙煎もしますが、オリーブ茶は蒸すんです」
お茶にする技術は製茶機メーカーと、葉っぱのエキス抽出技術などは、香川大学農学部や県の発酵食品研究所と共同研究して、3件の特許をとった。
果実ならない茶畑

「始めは木を剪定(せんてい)して、捨てていた葉っぱをお茶にしていました。剪定は年に1度ですし、枝先を摘みすぎると果実がならない。それで低木に仕立てて、茶畑専用にしました」
葉っぱの収穫は、5月の初めと8月の前半、9月の末から10月にかけて年に3回、茶摘機で刈り取る。だから茶畑のオリーブの木は果実がならない。
近未来のライバルは九州
「本場の本物」を目指したオリーブオイルは、葉っぱの加工を機に、新しい事業へとスタートした。植松さんは、ある商品の開発をベンチャー企業と組んで進めているが、まだ発表できないという。
オリーブの栽培規模が拡大した。振興特区認定から8年目の11年度、110ヘクタールに達した。イタリア料理ブームや食の安全意識も強くなった。耕作放棄地を活用して、就農する脱サラ組もある。
一方で、九州各県がオリーブ産地化に取り組んでいる。近い将来のライバルだが、栽培面積、生産量日本一の小豆島は、気象条件に影響されるオリーブの安定生産が課題だ。
植松さんには、それよりもっと大きな夢がある。瀬戸内海一帯を地中海沿岸のようにオリーブ地帯にして、農業、産業、観光を発展させる「瀬戸内オリーブ・コンビナート構想」だ。
オリーブハマチ誕生
県の水産試験場が、この粉末をエサに混ぜて与えたところ、一番効果の現れたのがハマチだった。07年、3千匹の養殖試験で、肉質が酸化、変色しにくい、魚臭さも少ない「オリーブハマチ」が誕生した。
08年にオリーブ植栽100周年、ハマチ養殖発祥80周年の記念事業として販売を開始、消費量が増えて、11年度は、香川県漁連によると、15万匹近くが出荷されたという。
搾油後の果実を乾燥飼料にして、肉質を高めた「オリーブ牛」も人気を呼んでいる。オリーブの用途はますます広がり、島を越えて新しい果実をもたらしつつある。
植松 勝太郎 | うえまつ かつたろう
- 1945年 内海町(現小豆島町)生まれ
1968年 明治大学農学部卒業
1973年 ヤマヒサ醤油入社
1983年 代表取締役就任
- 写真

株式会社ヤマヒサ
- 所在地
- 小豆郡小豆島町安田甲243
TEL:0879-82-0442/FAX:0879-82-5177 - 会社設立
- 1951年
- 代表者
- 植松 勝太郎
- 資本金
- 1000万円
- 従業員数
- 27人
- 沿革
- 1932年 創業
1951年 ヤマヒサ醤油株式会社となる。資本金200万円
植松 正 代表取締役に就任
1980年 ヤマヒサ醤油株式会社を社名変更。株式会社ヤマヒサとなる
1983年 植松勝太郎 代表取締役に就任
1989年 自社でオリーブの栽培を始める
1998年 自社農園栽培オリーブオイル発売
2003年 オリーブ振興特区第一号参入企業に認定される
- URL
- http://www.yama-hisa.co.jp/
- 確認日
- 2018.01.04
おすすめ記事
-
2019.03.07

300年続くオリーブ王国をつくる
小豆島ヘルシーランド 社長 柳生 敏宏さん
-
2017.07.20

美味しいオリーブで 地域を元気に、健康に
瀬戸内オリーブ 社長 松浦 玲子さん
-
2024.07.01

オリーブ水産物3種に「オリーブサーモン」の本格販売スタート
香川県
-
2022.06.02

全国初の機能性表示食品オリーブオイル
エキストラヴァージンオリーヴオイル(プラチナラベル 小豆島産)/小豆島ヘルシーランド株式会社
-
2020.09.03

讃岐のイメージ
野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸
-
2020.07.16

「オリーブ」三部作を読む
香川県教育委員会 教育長 工代 祐司
-
2017.08.03

手延べの技を生かして パスタ麺の断面は「凸型」
香川県知財総合支援窓口を活用 共栄食糧の「オリーブパスタ」
-
2015.06.18

オリーブの街で
香川県教育委員会 教育長 工代 祐司
-
2026.02.05
NEW

デジタルとアナログの融合で「麺のエキスパート」へ
まるみやホールディングス 社長 宮谷 和宗さん
-
2026.01.01

“移動”を支えるプラットフォーマーへ
トヨタカローラ香川 社長 向井 良太郎さん
-
2025.12.18

“現場知る強み”活かし 地域・お客さまを元気に
香川銀行 頭取 有木 浩さん