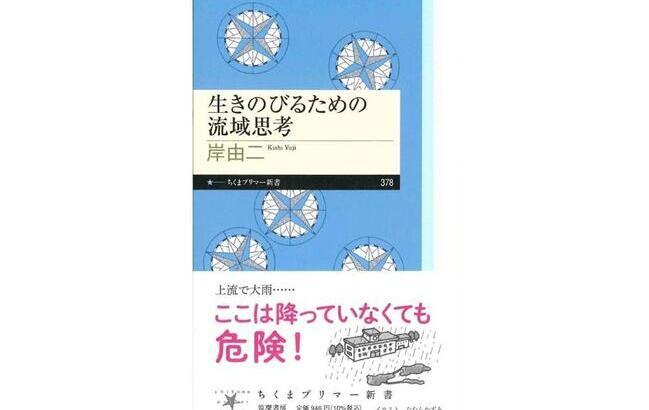
治水や自然保護に関する国や自治体の審議会委員を長く経験した研究者であり地域の防災活動に関わってきた市民でもある著者は、温暖化豪雨時代の入り口にいる今の状況に対して、社会は長きにわたり適切に対応できずにきたと言います。水土砂災害は河川が引き起こす、と今までは気象庁も国土交通省も強調してきました。著者は、私たちが今確認すべき重要なポイントは、氾濫を引き起こす構造として河川は直接的な原因に見えるが「その河川に大量の雨水を集める大地の広がりは流域であり、雨水や降水による氾濫やさらにそれらを水土砂災害を引き起こす川の流れに変換するのは流域という地形であり生態系」だと述べます。
そして昨年7月、行政の方から激変ともいえる方針の大転換が行われました。国土交通省の河川分科会という審議会が「流域治水」つまり水土砂災害を流域という枠組みで総合的に進めるという宣言、私は知りませんでしたが、日本の治水の歴史でいえば革命的ともいえる方針を発表しました。明治以降、日本の治水は専門的で大規模な技術に頼る治水を追求してきました。現代の治水は河川、下水道を効率的、合理的に管理改造し氾濫を抑えていく道を追求してきました。
そのための法律は基本二つあるということを初めて知りました。一つは河川法です。蛇行を直線的にしたり、浚渫(しゅんせつ)したり、土手を強靭にし、ダムや遊水地を工夫したりします。もう一つは下水道法で、この法律は下水処理以外にも地下、地上の下水路を整備し、雨をポンプ場経由で川や海に排水したり、地下に巨大なダムのような施設をつくって貯留したりする仕事も下水道法の管理するところです。しかし豪雨が頻発する現代、この二つの法律による整備や管理にどれだけ力を入れても、限界が見えてきました。そこで出てきたのが「流域治水」です。詳しい取り組みの事例は本書をご覧いただきたいと思います。
香川県には大きな川はありませんし、一級河川は土器川だけです。そんな土地柄だけに川とともに生きるという感覚はほとんどありません。しかし水害は決して他人事ではありません。
山下 郁夫
宮脇書店 総本店店長 山下 郁夫さん
- 坂出市出身。約40年書籍の販売に携わってきた、
宮脇書店グループの中で誰よりも本を知るカリスマ店長が
珠玉の一冊をご紹介します。 - 写真

宮脇書店 総本店店長 山下 郁夫さん
おすすめ記事
-
2025.01.03
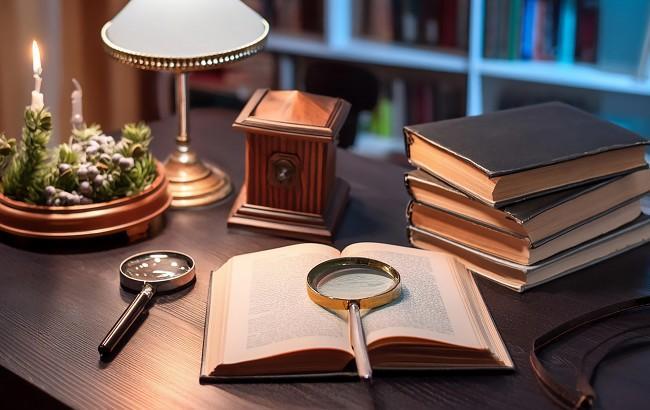
いつも、そばに
宮脇書店 総本店店長 山下 郁夫
-
2024.12.19
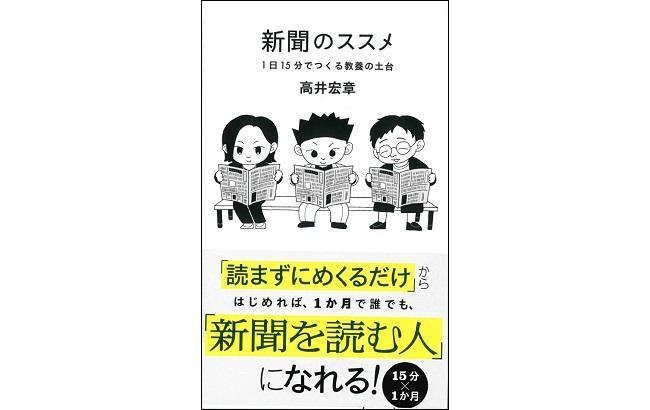
新聞のススメ
1日15分でつくる教養の土台著:高井 宏章/星海社
-
2024.10.17
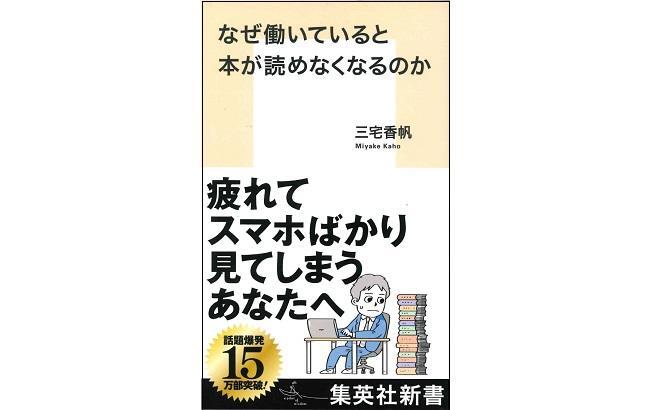
なぜ働いていると本が読めなくなるのか
著:三宅 香帆/集英社
-
2024.08.01
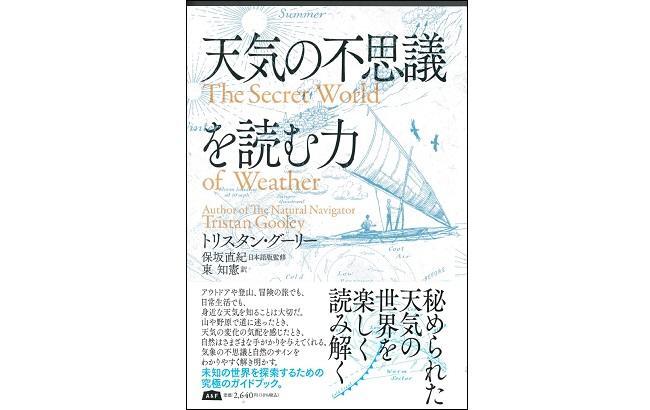
天気の不思議を読む力
著:トリスタン・グーリー/エイアンドエフ
-
2024.07.04
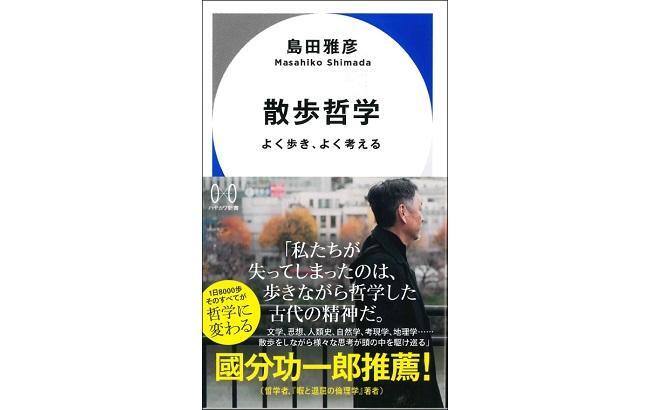
散歩哲学 よく歩き、よく考える
著:島田 雅彦/早川書房
-
2024.06.06
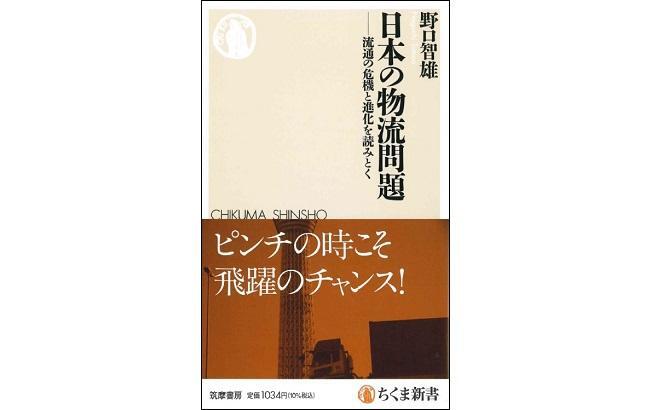
日本の物流問題-流通の危機と進化を読みとく
著:野口 智雄/筑摩書房
-
2024.01.04
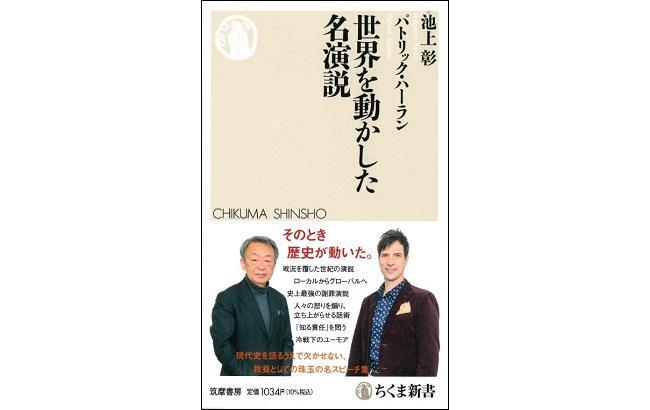
世界を動かした名演説
著:池上 彰、パトリック・ハーラン/筑摩書房
-
2023.12.07
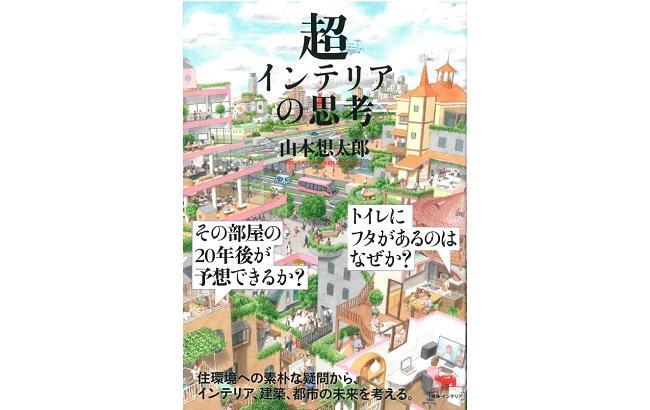
超インテリアの思考
著:山本 想太郎/晶文社
-
2023.11.02
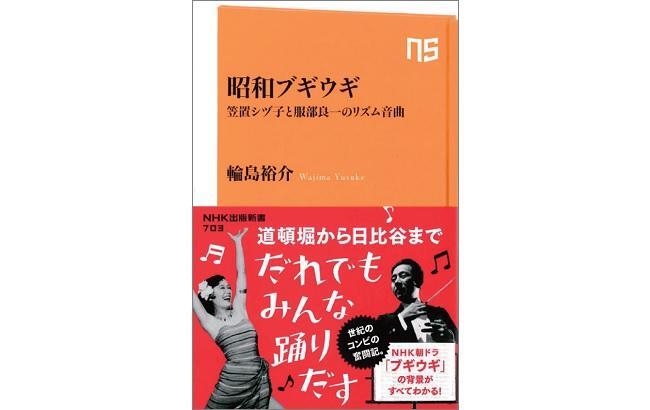
昭和ブギウギ
笠置シヅ子と服部良一のリズム音曲著:輪島 裕介/NHK出版
-
2023.10.05
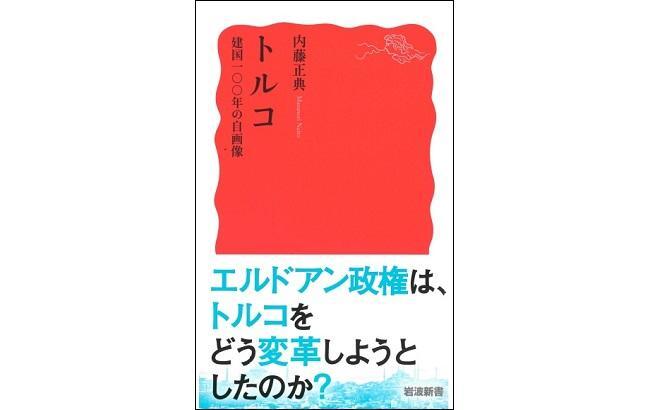
トルコ 建国一〇〇年の自画像
著:内藤 正典/岩波書店
-
2023.09.07
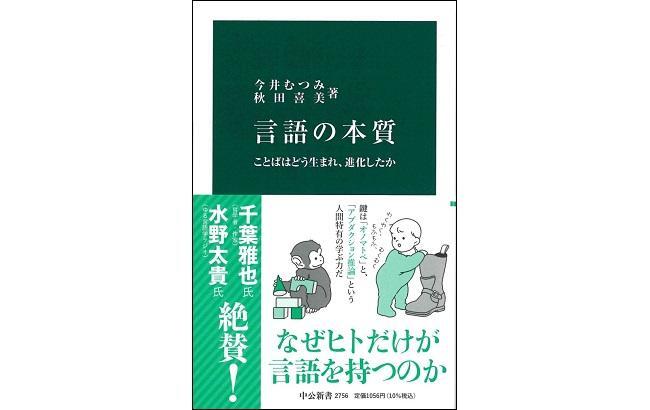
言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか
著:今井 むつみ、秋田 喜美/中央公論新社

















