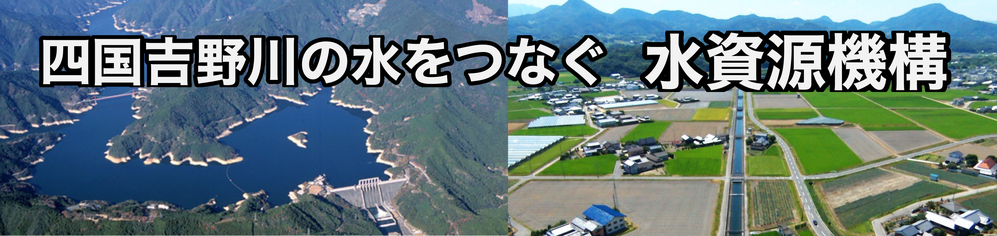みらプロ意見交換会(保護者、地域の人、先生等)
写真提供 西川真理子さん
先日、2022年に御一家で島に移住され、現在、男木小中学校のPTA会長をつとめる、なかがわまりめさんから島での子育てについてお話を伺いました。
男木小中学校の再開は2014年。2013年に帰省した福井大和さんが、子どものいない島の現状にショックを受け、家族一丸となって学校の再開に奮闘された話は有名です。
子どもたちが絶えない島をつくろう。福井大和さん、順子さん御夫妻は、NPO法人男木島生活研究所を立ち上げ、子育て世代の移住支援に尽力するとともに、男木島図書館の開設など子育て環境の整備にも力を注がれました。
こうした中、西川御夫妻ら2016年移住組の子育て世代が中心となり、「島だからこそできる教育を考えよう」と、2019年に「男木島、未来の教育プロジェクト(みらプロ)」が始まりました。
その目的には、島の学校として未来の教育の方向性の検討と実行を進めていく、新しい学習の形を学び、取り入れ、事例として公開していく、このプロジェクトを通して、子育て世代の移住者を増やしていくことの3点が掲げられています。「最初は学校の先生方も戸惑ったかもしれませんね」とまりめさん。
今年の1月11日、「男木島、移住相談会in東京」が有楽町のふるさと回帰支援センターで開催されました。なんと、この企画は男木小中学校の子どもたちの発案で、相談会には2人の小中学生が参加し、島での暮らしの様子を見事にプレゼンしたそうです。
ここ数年、学校とみらプロが連携して「やってみたいことを実現する活動」を総合学習の時間に取り組んでいます。その中で「友達を増やしたい」「じゃあ島に住む人を探そう」「それなら東京で男木島のPRをしよう」となったそうです。
男木島をこよなく愛し、それを行動に移せる子どもたちが確実に育っています。学校、保護者、地域が協力・連携した男木島独自の教育方法の模索が徐々に形となって表れてきたように思えます。
おすすめ記事
-
2025.10.02

暮らしや人生にそっと寄り添って
生活協同組合 コープかがわ
代表理事 理事長 亀井 愛知さん -
2024.04.04
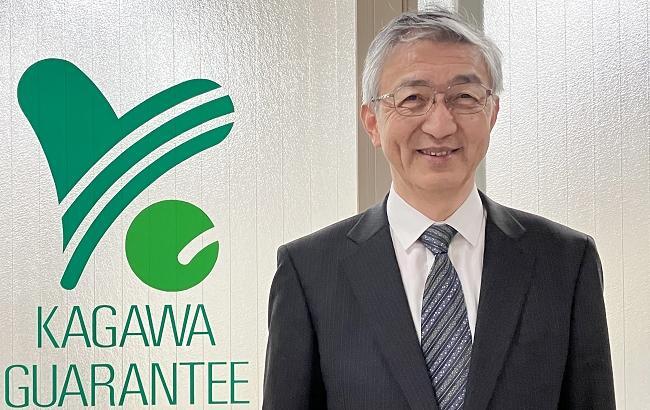
県経済の要たる中小企業を支えたい
香川県信用保証協会 会長 西原 義一さん
-
2023.01.05

どんなことでも気軽に相談を
香川県弁護士会
-
2022.12.15

地域を知るまち歩き
防災士 高橋 真里
-
2022.10.06

誰もが楽しく可能性を切り拓く場所に
公文教育研究会 高松事務局 局長 土方 誠さん
-
2022.08.18

「高橋さんの防災は、この地で育まれたんですね」
防災士 高橋 真里
-
2022.04.21

非効率でも対話を大切にしていきたい
株式会社UMOGA 社長 蒲生 宰実さん
-
2022.04.07
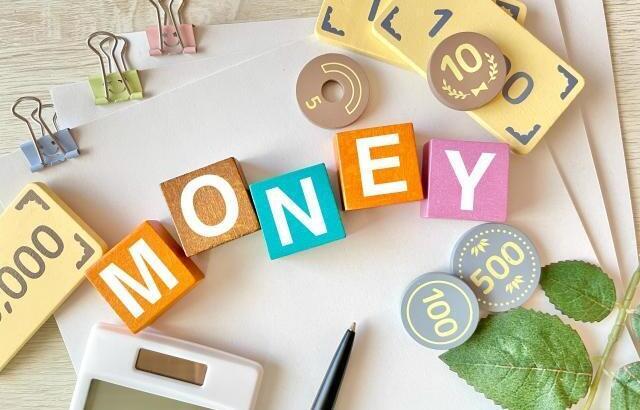
「当たり前」を守り続ける
日本銀行 高松支店長 高田 英樹
-
2021.09.02

東かがわ親子ジオクルーズ
香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 長谷川修一
-
2021.08.05

人とのつながりが人生を豊かに
特定非営利活動法人 子育てネットひまわり/代表理事 有澤 陽子さん
-
2021.03.18

「Withコロナ」で前向きに変化していく
株式会社DaRETO 城石果純さん