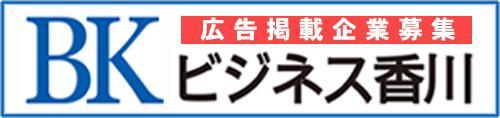宇多津の大束川東岸にある「海南行」の碑
頼之は、足利尊氏(あしかがたかうじ)が後醍醐(ごだいご)天皇に反旗を翻した時、父頼春(よりはる)とともに阿波から四国に入り、南朝勢力を駆逐しながら阿波と讃岐で地盤を築き、ついには四国4国の守護職を占めて四国管領といわれました。そして、香川郡岡(現在の高松市香南町)に居館を築くとともに、その本拠地を宇多津に置きました。
義満は、二代将軍の父義詮(よしあきら)が病により死去すると、11歳で三代将軍となりますが、この時、宇多津にいた頼之は京へ呼び出され管領に任じられます。1367年のことです。義満が幼少の頃の室町幕府は、南朝との抗争がいまだ続き、また幕府内部でも紛争が続いていましたが、頼之は、義満を養育する一方で、花の御所の造営や守護に荘園の年貢の半分を徴発する権限を認める半済令(はんぜいれい)を施行するなど、「名執事」として不安定だった室町幕府の基礎を固めます。しかし、その采配ぶりを妬む諸将との対立を招き、康暦(こうりゃく)の政変により、京から宇多津へ下野します。頼之はこのときの心境を「海南行」という漢詩に綴っています。その後、再び義満に召し出されて京に戻り、幕政に返り咲いて南北朝が合体した1392年に、64歳で死去します。
頼之の功績により、細川一族は室町幕府において確固たる地位を占め、特に頼之系統は京兆家(けいちょうけ)といわれ、その当主は、讃岐・摂津・丹波・土佐の4カ国を世襲し、中でも讃岐がその本国的存在でした。これは讃岐を押さえれば瀬戸内海の海上交通権を掌握できたことによるものと思われます。京兆家は、応仁の乱で知られる勝元(かつもと)とその息子の政元(まさもと)の時代に最盛期を迎えますが、頼之から政元に至るまでの約150年間は、京兆家の本拠地であったことから讃岐が日本の中央政治に最も近かった時期といえるでしょう。
讃岐には今も頼之に由来する神社、祭りなどが多く残っており、また、頼之に従って家臣として讃岐入りした東国武士が土着し、今もその末裔たちが活躍しています。
歴史ライター 村井 眞明さん
- 多度津町出身。丸亀高校、京都大学卒業後、香川県庁へ入庁。都市計画や観光振興などに携わり、観光交流局長を務めた。
- 写真

歴史ライター 村井 眞明さん
おすすめ記事
-
2023.06.01

美濃から来讃した生駒氏
シリーズ 中世の讃岐武士(34)
-
2023.04.20

九州で島津軍と戦った讃岐武士
シリーズ 中世の讃岐武士(33)
-
2023.03.02

秀吉軍と戦った讃岐武士
シリーズ 中世の讃岐武士(32)
-
2023.02.02

土佐武士の讃岐侵攻⑥(東讃侵攻)
シリーズ 中世の讃岐武士(31)
-
2022.12.15

土佐武士の讃岐侵攻⑤(十河城包囲)
シリーズ 中世の讃岐武士(30)
-
2022.11.03

土佐武士の讃岐侵攻④(香西氏の降伏)
シリーズ 中世の讃岐武士(29)
-
2022.10.06

土佐武士の讃岐侵攻③(中讃侵攻)
中世の讃岐武士(28)
-
2022.03.17

イリコの島に残る戦国秘話
中世の讃岐武士(23)
-
2022.02.17

三好の畿内奪還の戦いで信長軍と対峙した讃岐武士
中世の讃岐武士(22)
-
2021.12.16

讃岐を支配した阿波の三好氏
中世の讃岐武士(20)
-
2021.11.18

東讃から始まった讃岐の戦国時代
中世の讃岐武士(19)