
2001年、子どもが作る「弁当の日」を始めて2年後、著書「弁当の日がやってきた」(自然食通信社)を出版したときのことだ。
「好き」という言葉には不思議な力がある。魔法のように願いをかなえる。小学生のときから先生が好きだった。採点を手伝い、友だちに勉強も教えた。そして子供が大好きで教師になった。
「弁当の日」は、そんな竹下さんの、子どもが育つ環境を整えたいという願いからだ。子どもたちと弁当との対話が、魔法のように、親も学校も、そして社会も変える。
自分でやれば分かる
「大変な苦労をして、給食を大切にしてくれることを、食べ残しの多い子どもたちに気付かせるのが校長の仕事だと思いました」
どうしたらいいか、会議の場で考えた。子どもたちが自分で作ったら、毎日食べている給食のありがたさが分かる。料理を体験させればいいと気づいた。
覚悟としたたかさ
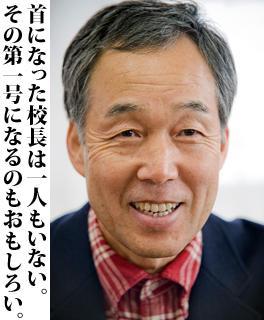
「その第一号になるのもおもしろい」。竹下さんは、決意した。学校経営で「前例主義」の必要性を認めながら、「私が前例になる」の姿勢を貫いた。やみくもにぶつかるのではなく、覚悟を秘め、したたかに校長職を10年間務めた。
買い出し、献立、調理、片付けの全部を子供にやらせる「弁当の日」を宣言したとき、教職員はためらった。PTAの役員は無理だと言った。
家庭で作る「弁当の日」は、学校教育の枠を超える。包丁とコンロを使うから、けがと火災が怖い。生の肉や魚は食中毒が怖い。でもリスクばかり論じても前に進めない。竹下さんは反対を押して見切り発車させた。
「始めませんか子どもが作る弁当の日」(自然食通信社刊)で対談した鎌田實・諏訪中央病院名誉院長(63)は、「難問を投げかける保護者や地域の声に、トップがどう処理するか教師たちは見ている。彼はその目を繊細に意識して、ダイナミックな戦略を仕掛けた」と表現した。
※鎌田 實
膨大な累積赤字を抱えていた長野県諏訪中央病院を立て直した功労者で、地域医療の在り方を根底から改革した。住民と共に作る医療を書いた著書「がんばらない」はテレビ化された。
ルールと約束
毎朝10分から15分、全校生徒一斉に好きな本を読ませる。でも感想文は書かせない。竹下さんは、この簡単な取り決めがポイントだと感心した。
「弁当の日」は三つのルールと一つの約束がある。子どもだけで作ること。5、6年生だけがやる。10月から翌年2月まで月1回のペースで年5回。そして出来具合を親や先生が評価しない約束だ。
料理の基礎は学校で教えるから、「親は手伝わないで」と何度も念を押したら、親のブーイングが少しずつ減った。
2001年10月19日、最初の「弁当の日」の給食時間、子どもたちは照れくさそうに、ちょっぴり誇らしげに食べた。弁当箱は、みんなきれいに空っぽになった。
※朝の読書運動
1988年、船橋学園女子高校・現東葉高等学校で林公・大塚笑子両教諭の提唱・活動をきっかけに全国に広まった。特に小学校で盛んである。
社会につながる弁当
――「気がついたことがあります。ぼく、お米を作っていません。野菜を作っていません。作ってくれた農家の人がいるんです。このサケ、海で捕っていません。捕ってくれた漁師さんがいるんです・・・その人たちのおかげで弁当を作れたんです。だから、ぼくは1人で弁当を作ったんじゃないんです」。私は小躍りしたい気分で話を聞いている。「できる!を伸ばす弁当の日」 (編著 竹下和男:共同通信社)より。
「料理が楽しいという感覚は、小さいときほど植えつけられます。味覚の発達は3歳から9歳までとされていて、台所に立ちたがるのは子どもの本能です」
11年前に始まった「弁当の日」の1期生は、いま22歳になった。2年前の成人式でとったアンケートでは、「食事を大変よく作る」55%、「まあまあ作る」15%、合計70%が自分で食事を作っていた。去年の成人式の2期生は、それが81%と増えた。
広がる「弁当の日」

竹下さん撮影
「姉の鳥山敏子の紹介で、自然食通信社から、『弁当の日がやってきた』を出版したんです。受賞はそれがきっかけです」
全国の食育に影響力のある人たちやマスコミに本を贈った。1年間で130件の取材を受けた。全国から講演依頼を受けたが、実行する学校は増えなかった。
そんなとき、西日本新聞社の佐藤弘と渡辺美穂の両記者が来た。この新聞社の長期企画「食卓の向こう側」の第8部に掲載され、「弁当の日」が九州から波紋を起こし始めた。2012年2月末、全国の約1千校で実施されている。
※鳥山敏子
香川大学卒業。青梅市で小学校教員になる。1980年、中野区立桃園第二小学校で行った「ニワトリを殺して食べる授業」、そして「東京賢治の学校」などの革新的な教育実践で知られている。
※西日本新聞
本社は福岡市。西日本新聞と西日本スポーツを発行。福岡県全体をカバーする地元新聞社で、九州各県にネットワークを持つ。
給食費未払いゼロ
子どもは宝だ。希望という宝だ。竹下さんは子どもを育む環境を整えるために、親と学校の信頼を地域ぐるみで作ると宣言した。
「車のローンや衣服費、遊興費にはお金を払っても学校集金を払わないことは、『お前の教育より車などを優先する』というメッセージになる。子どもは、そのことに気づいている」と書いたプリントを地域に配った。
夜、家まで訪ねて集金もした。法的な手続きも取った。竹下さんは翌年のPTA総会で保護者に報告した。「全員が払ってくださいました。未払いはゼロです」
「弁当の日」で教員や親たちも学んだ。一歩前に踏み出せば「新しい前例」になるのだ・・・。
学者より子どもを選んだ
安藤昌益は、封建社会を厳しく批判した先鋭的な江戸中期の思想家で、著書は、共産主義や農本主義、エコロジーに通じるとされて、レーニンにも影響を与えたという。
「内容があまりにも過激ですから、弾圧を避けるために、当たり障りのない内容の刊行本と過激な秘蔵本の2種類に書き分けたというのが、従来の説だったんです」。竹下さんは、書き分けたのではなく、思想が変わっていったことを明らかにした。
昌益の書籍は漢文で書かれている。用語なども彼独特の言葉が多い。「昌益が使った特有の用語の頻度を数えて表にしたら、著作の書かれた順番がグラデーションで見えてきて、思想が発展・円熟した過程を証明できることを発見したんです」
竹下さんは卒論執筆時に著書の実物は調べていなかった。岩波書店の日本古典文学大系や文庫に収録されている、一部だけを分析した推測だった。
「著作の実物すべてにあたって論文を完成し、研究者になりたいと、教師になってからも勉強を続けました」。しかし大学教授への道を捨て、新学説の権利も放棄して卒論の要約を八戸図書館に送った。これが昌益研究のその後を変えた。
竹下さんは過去の昌益より、未来を生きる子どもたちの、大人をはるかに超える感性や好奇心にひかれたのだ。
※安藤昌益
1703~62年。江戸時代中期の医者・思想家。秋田藩出身。
竹下 和男 | たけした かずお
- 問い合わせ先
- 綾歌郡綾川町滝宮201番地
TEL:090-7625-3992/FAX:050-3793-0267
E-mail:bentounohi@gmail.com - 1949年 香川県綾川町生まれ
香川大学教育学部卒業後、小学校教員9年、
中学校教員10年、教育行政職9年を経て、
2000年度より綾南町立滝宮小学校校長
2003年度より国分寺町立国分寺中学校長
2008年度より綾川町立綾上中学校長
2010年3月退職
4月からフリーで執筆、講演活動を行っている - 著書
- 「安藤昌益」(共著・光芒社)
「弁当の日がやってきた」(共著・自然食通信社)
「台所に立つ子どもたち」(共著・自然食通信社)
「始めませんか 子どもがつくる"弁当の日"」(共著・自然食通信社)
「泣きみそ校長と弁当の日」(共著・西日本新聞社)
「できる!を伸ばす"弁当の日"」(編著・共同通信社)他
- 写真

おすすめ記事
-
2013.04.18

「頭脳は無限」の教え胸に 西日本屈指の養鶏企業へ
新延孵化場 社長 新延 修さん
-
2014.06.05

地域とともに車と楽しむ人生
株式会社伊賀モータース 代表取締役社長 伊賀 知由さん 伊賀 雄一さん
-
2014.11.06

結婚式は絆と絆の交差点
ザ・チェルシー(マツノイパレス) 代表取締役社長 住田 浩さん
-
2026.01.01

“移動”を支えるプラットフォーマーへ
トヨタカローラ香川 社長 向井 良太郎さん
-
2025.12.18

“現場知る強み”活かし 地域・お客さまを元気に
香川銀行 頭取 有木 浩さん
-
2025.12.04

財産は「人」。安全・安心・快適を届ける
西日本高速道路エンジニアリング四国
社長 後藤 由成さん -
2025.11.06

“ケタ違い”のものづくりで世界の物流を支える
マキタ 社長 槙田 裕さん
-
2025.10.16

次世代を支える担い手づくりへ
JA香川県 代表理事 理事長
北岡 泰志さん -
2025.10.02

暮らしや人生にそっと寄り添って
生活協同組合 コープかがわ
代表理事 理事長 亀井 愛知さん -
2025.09.04

企業や暮らしを「システム」で支える
ロジック 社長 山﨑 直樹さん
-
2025.08.21

「ここに来て良かった」 生徒一人一人に寄り添って
学校法人村上学園 理事長
村上学園高等学校 校長
村上 太さん

















