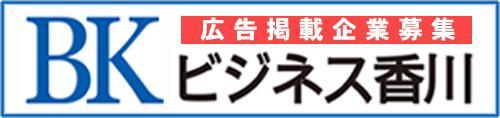母体の陣痛、胎児の心拍数などの検査データはモバイル通信で電子カルテに送られる=高松市林町のミトラ
社長の尾形優子さんは大学、大学院時代に原子核工学を専攻。医療用の多極磁石や高周波リニアック(線形加速器)などを研究するいわゆるリケジョ(理系女子)だった。高松市のソフトウエア会社に勤めていた2000年、四国4県で取り組む経産省の電子カルテ事業に香川の代表企業として参加した。実証実験に加わっていた産婦人科医が言った「出産情報がデータ管理できたら助かるわ」という一言に「ビビッときました」
ほとんど普及していない産科用電子カルテを作る。周囲は無謀と言ったが、直感を信じて2年後、ミトラを立ち上げた。「市場が元々無いので最初は全く売れませんでした」
その先見性と行動力で尾形さんは新たな市場を生み出し、起業から10年余りで海外をも視界に捉えた。
大手も敬遠する産科用電子カルテ

「データを見ることで、どうすればいいのかという次の手がすぐ打てます。ドクターも妊婦さんも安心して出産に臨むのを支えるシステムです」
電子カルテと言えば、今でこそよく耳にするが、それでも普及率は全医療施設の15~20%程度。「産科用」に限定すると、ほんの数%と言われている。広まっていないのには理由がある。
産科用カルテには途中で患者番号が増えるという特異な性質がある。加わるのは赤ちゃんの番号だ。ある大学病院には二十数億円の電子カルテシステムが入っているが、産科だけ途中で番号を増やすというプログラムを組むのは技術的に極めて難しいそうだ。また、その2人分のデータを一般的な患者より長い、約10カ月間管理しなければならない。データ量は膨大になる。
さらに、産婦人科医や助産師は診療情報を記録する助産録の提出が法律で決められているが、この助産録、定型の書式がない。「分娩情報を載せなさいよというルールしかないので、何を記載するかは病院独自。つまり電子カルテにすると、病院ごとに項目が違う『完全オーダーメード』になるんです」。それぞれの病院に応じてシステムを組むのには、時間と労力がかかる。プログラミングも複雑で大量生産は難しい。そのため大手も産科用電子カルテには手を出さなかった。「市場が無い」大きな理由の一つだ。
「絶対に必要」と信じて

妊婦と胎児のデータを管理する
「ハローベイビープログラム」
「打たれ強いんですね。普通の人だったらあきらめていたんじゃないかと思います。でも知られていないだけ。知ってもらえさえすれば、絶対に必要とされると信じていました」
200の病院を営業回りする目標を立てた。学会など医者が集まる場所もしらみつぶしに訪ね歩いた。
初めて買ってくれたのは、千葉県の亀田総合病院。全国でも有数のIT化に積極的な病院だったが、やはり産科だけは電子カルテが導入できていなかった。ミトラの噂を聞きつけ、担当者が高松まで訪ねて来た。プレゼンを重ね、記念すべき第1号の販売に成功。起業して3年目のことだった。「その時はやった~って。本当にうれしかったです」
評判は、全国の病院や自治体に口コミで広がった。まずは「知ってもらわなければ」と、時には費用を負担してシステムを貸し出した。「完全オーダーメード」の難問には、医師が要望しそうな診察項目を予測し、事前に数万パターンの組み合わせを作成。納品期間を短縮させ、病院ごとのきめ細かなカスタマイズにも対応した。
現在全国で約100カ所の病院や治療院がこのシステムを導入しており、産科用の電子カルテでミトラは国内トップシェアを誇る。尾形さんが信じた「絶対に必要とされる」。間違ってはいなかった。
世界も必要としたシステム
「産婦人科医の数は特にへき地や過疎地で激減しています。遠野市ではこのシステムを入れてから出生率が上がりました」
それでも医療技術の高い日本では、元々異常分娩や、妊婦や胎児の死亡率は高くない。ミトラでは昨年から東南アジアへの展開を始めた。現在タイで7施設、ラオスで3施設。医療レベルや通信網がある程度発達している都市部と、医師不足に悩む山間部をネットワークで結んでいる。「南アフリカからも話が来ています。こういったITが威力を発揮する場所はまだ限られていますが、少しでも役に立てられたらと思っています」
起業後まもなくして、奈良や東京で妊婦の救急車たらい回し事件が起きた。尾形さんは「妊婦さんの状態が分からないから大きな病院へ行ってくれ、となったのではないでしょうか。病院間で連携して患者さんのデータが共有されていたら・・・・・・」と唇をかむ。遠野市がある岩手県は現在、ミトラのネットワークシステムを十数台導入。妊婦の救急搬送中、検査機器からダイレクトにデータが病院に送られ、医師が受け入れの準備を整えている。
自身も出産を経験した。大きな不安は無かったが、「自分に何が起こっているのか分からない状態だった」と当時を振り返る。診察・検査データが管理されることで、医師も助かり、妊婦も安心できる。そして、新たな命が生まれる―。尾形さんはこう話す。「リスクのある出産には速やかに対応し、リスクの低い妊婦さんには出産を楽しんでほしい。このシステムを世界中の人たちに役立ててもらうことで、出産や子育てにもっと優しい世の中になればうれしいですね」
◆写真撮影 フォトグラファー 太田 亮
尾形 優子 | おがた ゆうこ
- 大阪府高槻市出身
1981年 京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻
1991年 株式会社ファモス 画像処理部チームリーダー
経営企画室室長
1997年 株式会社アムロン 常務秘書
株式会社イノベイト 企画室室長
1998年度 診療所向け電子カルテ開発(経産省事業)に参加
2000年度 四国4県電子カルテネットワーク事業(経産省事業)に参加
2002年 株式会社ミトラ 設立
- 写真

株式会社 ミトラ Medical IT Laboratory(メディカルITラボ)
- 住所
- 高松市林町2217番地15 香川産業頭脳化センター406
TEL:087-869-8288
FAX:087-869-8377 - 設立
- 2002年10月10日
- 資本金
- 1200万円
- 事業内容
- ネットワークシステムの設計
コンピュータソフトの企画開発及び販売
コンピュータ及びソフトウエアメンテナンス業務
コンサルタント業 他 - 2004年 周産期電子カルテ「ハローベイビープログラム」リリース
2008年 健康診断結果自動判定システム「メタボリックカルテ」リリース
遠野保健福祉情報システム「遠野型すこやかネットワーク」が総務大臣賞受賞
2009年 岩手県周産期医療情報ネットワークシステム「いーはとーぶ」が
u-Japanベストプラクティス2009 u-Japan大賞受賞
ジャパン・ベンチャー・アワード2009起業家部門 中小企業庁長官表彰
- 確認日
- 2018.01.04
おすすめ記事
-
2021.05.07

一人でも多くの人の健康を支えたい
しん治歯科医院 院長 髙橋伸治さん
-
2020.09.03

患者さんに安心してもらえる存在でありたい
香川県医師会会長 久米川 啓さん
-
2019.07.18

“古い殻”を破り 生きる力を応援
高松市立みんなの病院 院長 和田 大助さん
-
2009.04.16

「選ばれる病院」へ
他業種から学ぶ病院経営キナシ大林病院 院長 鬼無 信さん
-
2019.01.17

患者に寄り添い 地域医療を支える
百石病院 院長 香西 由美子さん
-
2015.08.20

アートで 病院に安らぎを
四国こどもとおとなの医療センター 院長 中川 義信さん
-
2014.10.02

最新ハイテク機器で目指す機能分化
香川県立中央病院 院長 太田 吉夫さん
-
2014.01.03
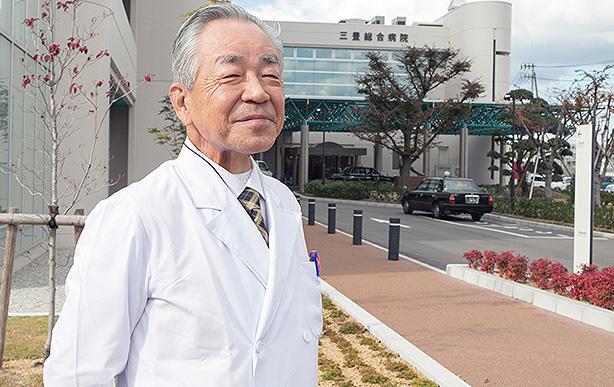
目指すは「地域医療」戦略は「先進医療」 三豊総合病院の経営力
三豊総合病院 企業長 広畑 衛さん
-
2013.03.07

生きざま問いつつ在宅専門の診療所
敬二郎クリニック 院長 三宅 敬二郎さん
-
2025.06.19

予防重視の口腔ケアで
「喜ばれる」歯科像を実現医療法人社団 しん治歯科医院
-
2023.02.02

保険薬局としての役割を発信していきたい
香川県薬剤師会