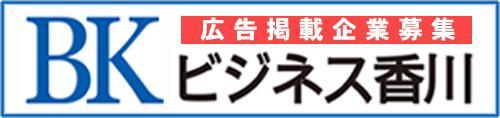そのためにまず必要だと考えているのが、インフラの整備だ。8の字ネットワークの完成や、国際的な視点をもった港湾など、基盤を整備することで地域経済の発展にもつながる。「インフラとは、文明をつくるものだと思います。太古の『世界4大文明』といわれた地域で土木技術が発達していたように、社会が変わるためにインフラは欠かせません」
同時にインフラは、防災時にも重要な役割を果たす。防波堤や、緊急車両の通行・物資輸送にも必要な道路。被害を最小限に抑えるために施設を整備するとともに、老朽化対策も視野に入れている。「今後、修繕が必要な施設が増えてくるが、市町村には技術職系職員が少ないことも課題の一つ。管轄する道路、河川などの整備、維持管理、防災などの業務を手掛ける整備局として、技術面でも支援していきたい」
震災時の対応を経験して

就任会見の様子
緊急車両の通行や物資の輸送に欠かせない阪神高速の一部が倒壊。代わりにどのルートを使うか、どう復興させるのか、予算の調整は……。数カ月ほど泊まり込みでの業務が続いたが、「あれほど災害対応に集中したのは貴重な経験でした。自分が現場の責任者だったらどうふるまうべきか、考える機会にもなりました」
防災について感じているのは、インフラだけでは対応できないということ。「職員も含めて災害時はどう行動すべきか常に考え、自治体とも連携して訓練しておかなければならない。何度も繰り返して」
その上で、地域の人にも積極的に情報を発信していきたいと考えている。「技術職の人間は『いいものをつくればわかってくれるだろう』という意識があるかもしれません。これからは、『なぜこの事業をやるのか』『私たちの施策は』などについて、日ごろから伝えるべきだと思います」。そうすることが、災害時にも生きてくるという。
「多・長・根」が大切

「日下川新規放水路工事現場」(高知県)を視察
「職員を含め若い世代には、専門分野以外の幅広い知識を勉強して、同じ会社、業界以外の人とも交流を深めてほしいと思います」
石川恭子
丹羽 克彦 | にわ かつひこ
- 略歴
- 1964年 東京都生まれ
1990年 早稲田大学大学院理工学研究科 修了
建設省入省
1996年 四国地方建設局土佐国道工事事務所調査第二課長
1998年 四国地方建設局企画部企画課長
2005年 近畿地方整備局京都国道事務所長
2009年 国土交通省道路局国道・防災課国道事業調整官
2017年 関東地方整備局道路部長
2019年 国土交通省道路局企画課長
2020年 四国地方整備局長
おすすめ記事
-
2023.12.07

『瀬戸の都』ブランドの確立を
香川県観光協会 専務理事 佐藤 今日子さん
-
2023.03.02
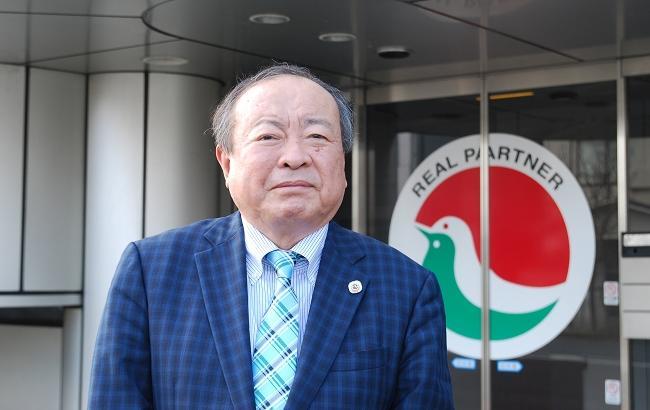
不動産を通じて地域活性化に貢献を
公益社団法人 香川県宅地建物取引業協会 会長 加内 雅彦さん
-
2022.04.07

人のつながりに感謝し1日1日を大切に
コンフォートホテル高松 マネージャー 熊谷 優太さん
-
2021.12.02

あるべき姿を考え、進んでいく
三井住友海上火災保険株式会社高松支店長 大矢邦雄さん
-
2021.02.18

「A・T・M」を心掛けて 地域に種をまく
中国銀行常務執行役員 四国地区本部長 西明寺康典さん
-
2015.12.03

海事から観光まで
四国運輸局長 瀬部 充一さん
-
2017.12.21

四国は大切なものが残る豊かな場所
NTTドコモ四国 執行役員四国支社長 立石 真弓さん
-
2018.07.05

四国愛とよそ者目線で 地域の企業を支える
日本政策投資銀行 四国支店長 久保田 和雅さん
-
2025.12.04

サンポート高松(その1)
工代祐司
-
2025.10.16

歴史ある町並みを守り、住み継ぐ挑戦
引田町家マッチングプロジェクト
-
2025.08.04

高松空港と台中国際空港が連携覚書
地域交流と利用促進へ高松空港