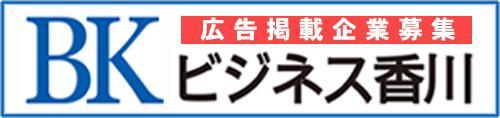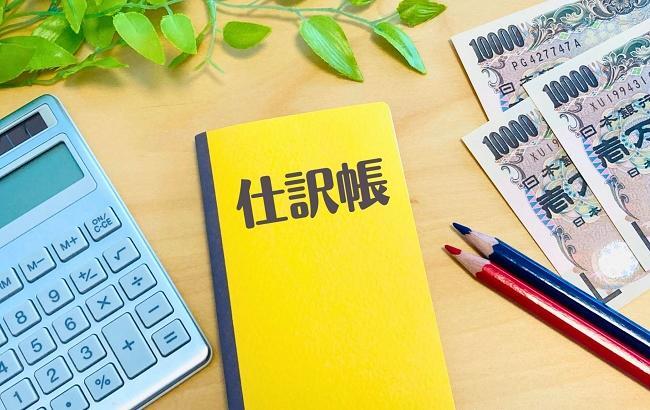
さて、この簿記。「読み・書き・算盤」と同様に学びの基礎と思う。現代経済社会では、数値で財政・財務状況を把握・分析し、経営判断する。この諸表類の作成の基が簿記だからである。まずは「しわけ」が大事となる。
「仕訳」という形で原因と結果の両面から取引を記録する複式簿記は、福沢諭吉が西洋式簿記を紹介してから発展したもので、お金の流れを帳簿に記載することから会計書類につながる。当然ルールがある。そのルールの支柱となるのが企業会計原則である。7つの一般原則があるが、8つ目ともいうべき重要性の原則がある。取引を特別扱いするかどうか決めるもので、全体の判断に与える影響があるかないかで処理を変えるものである。例えば、少額な備品は減価償却せず費用としてしまうなど金額の大小や内容の質で経営判断に影響がなければ簡略化するし、重要なら注記する。これらを学ぶ中で重要度の感覚が身につくし、仕訳に迷うような場合はどの原則に該当するだろうかと基本を考えるようになる、と思っている。
企業活動における「しわけ」は、選択という「仕分け」となる。例えば、価格転嫁かコスト削減か、拡張か現状維持かなど、あらゆる場面で判断がある。この「仕分け」は、原因と結果のバランスを考えた決断であり、主に経営者の役割と責任である。仕分けに失敗するのは、対象事案への情報が不足していた、認識が誤っていた、過去の成功体験に引きずられていた、といったことが多い。最近はSNSの普及により、怪しい情報までもが拡散しており、流言に惑わされる機会が多くなっている。ついついチェックを怠り、都合の良い判断をしてしまうことがある。何にでも原則はあり、仕分けの際に使える。何を拠り所にしているか基本に立ち返ること。法令等の規定が根拠とされているものは条文の確認を、解釈に間違いはないか、広く意見を取り入れているか、創業の精神、目的、理念に照らしてどうか等、「原点に戻る」という原則に従ってみることである。
原則どおりが正しい結末になるとは限らないが、私は選択に迷う時には、できるだけ原則を考えるようにしている。一般に認められたルールは自身が納得するからである。
香川県信用保証協会 会長 西原 義一
- 写真

おすすめ記事
-
2026.01.01

繁盛の神様
香川県信用保証協会 会長 西原 義一
-
2025.05.01

起業に関心を持ってみよう
香川県信用保証協会 会長 西原 義一
-
2025.01.03

地域経済を守るうえで必要な匠長づくり
香川県信用保証協会 会長 西原 義一
-
2024.09.05

成り立ちを知ることで、ありがたみがわかる
香川県信用保証協会 会長 西原 義一
-
2024.05.02

経営管理者のインテグリティ
香川県信用保証協会 会長 西原 義一
-
2024.12.19

「神は天にいまし、すべて世はこともなし」
四国なんでも88箇所 巡礼推進協議会会長 佐藤 哲也
-
2023.11.02

ボランティア活動と組織運営
株式会社人生百年サポート 代表取締役 十川 美加
-
2022.06.02

「年寄りの戯言」と「今の若いもんは」
四国なんでも88箇所巡礼推進協議会会長 佐藤 哲也
-
2025.07.03

「超量産拠点」の新たな価値を打ち出す
オリエンタルモーター 常務執行役員・高松カンパニー執行役員社長 五十嵐 淳さん
-
2025.06.05

憧れの背中を追いかけて、会社の利益を守るキーパーソンに
石井慶彦(いしい・よしひこ)さん/四国塗装工業株式会社 業務課 課長
-
2025.02.06

新たなソリューション提案で
地域の連携と発展に貢献したい三菱電機 受配電システム製作所 所長 吉田 大輔さん