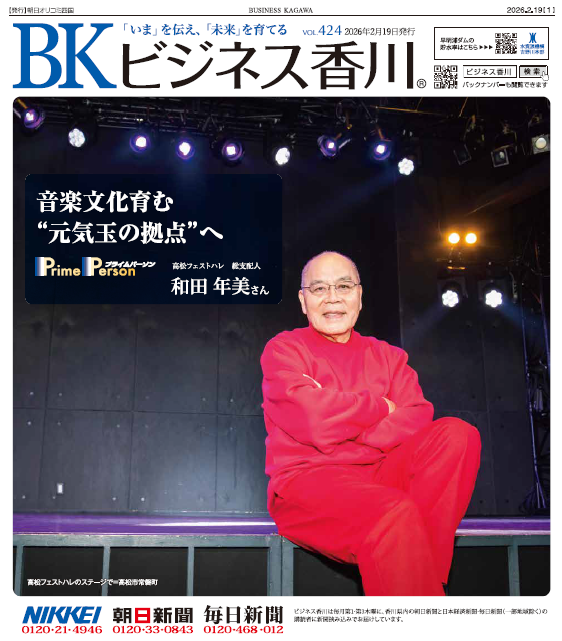不思議を追究しようと中学で化学クラブに所属。大学では有機化学を研究した。ある性質をもつ物質をつくる、という目的に向かって物質を合成していく。結果を予測しながら進めるが、8割以上は思い通りにいかない。だから、化合物がうまく合成できた時は充実感があったという。

第29回プログラミングコンテスト「自由部門」で
最優秀賞と優秀賞を受賞
地域の課題を掘り起こし、考える
地域の人や企業に話を聞きに行き、さまざまな課題を掘り起こす。その中の一つとして、塩江で昔走っていたガソリンカーを復活させ地域おこしにつなげるプロジェクトが進んでいる。担当の先生を中心に1~3年生がチームになり、昔の設計図をもとにガソリンカーの復刻に挑戦している。どういう結果を目指すのか、そのために何をどういう方法で進めるか、正解が一つではない課題に対して模索する。「自分の専門以外のことでも『この原理や技術を利用すればできるんじゃないか』と気づける感性、別の専門家と協力しながらチームとして成し遂げられるコミュニケーション力も磨いてほしいと思います」
19年度から実施する新カリキュラムは、専攻する学科の基礎的な力をつけた上で、専門以外の知識や技術も横断的に学べるよう設定されている。また、学内で発明コンテストやデザインコンペを開催し、自分のアイデアが社会でどう役立つのか提案できる力を養うほか、知的財産権について学ぶ機会もつくっている。
「自分が開発した製品が社会のニーズにマッチしているか、販売するには――といったことも考えられる“起業マインド”を身に付けた学生たちの中から、地域の課題を解決するベンチャーを立ち上げる事例が出てくると嬉しいですね」
人間的な成長を

共同研究をしていたインド・コルカタの研究所で
これまでのキャリアの中で、さまざまなタイプの研究者と出会ってきた。周りの注目を集める人、地味だがしっかり根をはって実績を上げる人・・・・・・考え方もやり方もスピードも違う。学生たちも自分の個性を大事にしてほしいと考えている。「違うと思ったら進路を変えてもいいと思います。焦らず、滞らず、自分が納得できる人生を送ってもらいたいですね」
石川 恭子
安蘇 芳雄 | あそ よしお
- 略歴卯
- 1953年 福岡県生まれ
1971年 岩手県立盛岡第一高校 卒業
1977年 大阪大学理学部化学科 卒業
1979年 大阪大学大学院理学研究科
有機化学専攻前期(修士)課程 修了
1981年 名古屋大学 教務職員
(化学測定機器センター)
1983年 広島大学 助手(工学部第三類応用化学講座)
1992年 米国 ネバダ大学・ボストンカレッジ
博士研究員
1994年 広島大学 助教授
(工学部第三類応用化学講座)
1998年 九州大学 助教授
(有機化学基礎研究センター)
2001年 広島大学 助教授
(大学院工学研究科物質化学システム専攻)
2003年 大阪大学 教授(産業科学研究所)
2018年 香川高等専門学校 校長
おすすめ記事
-
2025.02.20

人生やキャリアに迷った時に
頼れる企業でありたい株式会社マイナビ 香川支社 支社長 佐々木 康人さん
-
2024.10.03

モットーは「凡事徹底」
地域の元気を支えたい!中国銀行 執行役員・四国地区本部長 吉田 秀樹さん
-
2024.08.15
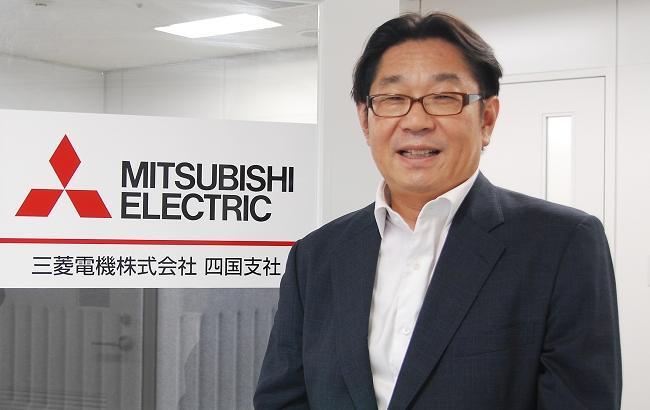
仕事の枠を超えていけ!
自由な視座が支えたキャリア三菱電機 四国支社支社長 木ノ下 英則さん
-
2024.06.20

日本を変える鍵を握るのは
自由でトガった若者たち香川高等専門学校 校長 荒木 信夫さん
-
2023.02.02

地域企業の成長を支えたい
日本公認会計士協会四国会 会長 久保 誉一さん
-
2021.12.16

見守り、背中を押すことで やりがいを感じる職場にしたい
パソナ・高松 支店長 三宅江利子さん
-
2020.03.19

人生の選択にかかわれることが、仕事のやりがい
パソナ・高松 支店長 土信田慶さん
-
2019.09.05

変化するから未来がある
NTT西日本 香川支店 支店長 北口哲也さん
-
2009.08.20

笑い(ユーモア)は人生を、世界を豊かにする。しあわせだと思う気持ちと感性を養って、ユーモアをもっと自分のものに。
大麻学園事務局長 中井 宏次さん
-
2010.12.02
経験を積み、自信を持つことで、人は成長する。バレーも仕事も同じことが言える。
サントリーフーズ 四国支店長 五味 康友さん
-
2011.07.21

野菜作りも人作りも同じ 上手に「ほったらかす」
三井住友海上火災保険 高松支店長 松永 司さん